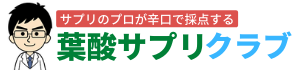回答6:将来の授業参観のためにも夫婦で名付けをしておくべき

こじかママ(1985年生まれ/子供3人/看護師)です。名付けは子どもの両親が決めるべきです。私たちは、主人と二人で話し合って決めました。
両親からは、「2人が初めてあげられるプレゼントだよ」と言われて、決定権は私たちにありました。「おじいちゃん、おばあちゃんになってもしっくりくる名前がいいんじゃない?」とアドバイスをもらいましたが、参考程度にしました。後々トラブルにならないように。
1人目の名付けは、「すべてにおいて良い方向に向かう画数の名前がいい!」と、主人に伝えました。主人も同じ意見で、後日買ってきてくれた名づけ本の中から、2人でいくつか出し合って、同じ意見の名前の漢字を見つけて決めました。
でも、生まれた子の顔を見たら全然イメージと違って(笑)、変更しました。前もって悩みに悩んで決めていても、しっくりこないことだってあるんです。
産むのは母であるまりぽんさんだし、育てるのは、まりぽんさん夫婦です。なので、名付けの決定権はお二人にあります。もちろん、両親や義両親の意見もありますが、そこは「私たちだけで決めたい!」と強く言うべきです。
夫婦で決めるべきこんなエピソードもあります。長男が小学2年生の時に、「自分の名前の由来」を発表する授業参観がありました。夫婦でたくさん考えた名前だったので、発表している姿を見て「成長したなぁ。みんなに名前の由来を知ってもらえて嬉しいな」と、色々な思いがこみ上げてきて、泣きそうになりました。
由来を調べていた時の息子も「ママとパパが決めてくれたんだね。この名前でよかった!」と、とても嬉しそうでした。なので、子どものためにも夫婦で決めるべきです。名前を具体的に示すのではなくて、雰囲気や、音や、画数など、こだわりたいところを話し合ってみると良いです。
回答7:両親に名付けから外れてもらって、夫婦だけで決める

ヨカっち(1976年生まれ/子供4人/自宅出産)です。ウチは子供4人とも、夫婦で相談して決めました。基本的には、こだわりが多い私が候補名を出していって、ダンナが「それはちょっと・・・」と言う場合にはやめるパターンでした。
夫婦では「漢字1文字で」が共通していて、私のこだわりは「普通に読める名前」で「イメージがかっこいい漢字」でした。ダンナのNGは「知り合いとかぶる」「イメージが気に入らない」のどちらかが理由でした。
3人目、4人目と、回を重ねるほどなかなか決まりませんでした。最後には漢和辞典とにらみ合って、脳みそを絞ってひねり出した感じです。最終的に、なんとか落ち着きどころを見つけ、無事に4人目まで名前をつけることができました。
さて、相談者さんのお家では両家のご両親までが名付けに参加されているのですね。それではややこしくなるのもわかります。私が強くおすすめするのは、「ご両親には名付けから外れていただく」ことです。実はこの考え方は、今後の子育てにずっとついて回ることです。
お子さんにとって、一番の存在はパパとママなのです。子育ての主導権は夫婦2人が持つべきで、最初からご両親にもそう理解してもらう必要があります。名付けではないですが、私も子供のことで介入されたことがあって、お断りしてきました。もちろん、ケンカにならないよう「次の○○では頼りにしています」的にやんわりと気持ちを伝えました。
なので、「子育ての主導権は夫婦2人が持つ」ことをダンナさんと再確認してください。「2人の赤ちゃんなんだから、2人で決めよう」と。ここさえ夫婦で合意できれば、あとは各両親を説得して、2人だけで決めればいいのです。ダンナさんと意見が合わなかったら、ウチのように新しい案を延々と考えれば公平ですよね。
私も「この名前にしたい!」と思っていたのを断られたときには凹みましたが、「じゃあこれは?」と返すダンナの候補も気に入らなければ即ボツったし、お互い様でした(笑)たくさん出していくうちに、いつか(疲れて?)「それにしよう!」と決まると思いますよ。
回答8:出産の苦労がわかると、旦那が折れてくれるかも
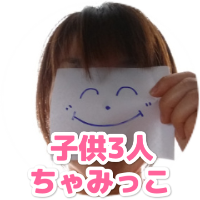
ちゃみっこ(1976年生まれ/子供3人/調理師)です。赤ちゃんの名前は一生のものですし、みんなそれぞれ譲れない想いはありますよね!うちも名付けのときは、私、旦那、旦那の親、3人目に至っては、長男、次男が意見を曲げずに、激戦となりました(笑)
1人目のときは、産まれる前から名付けの本やサイトを見て、私なりに候補を挙げていたのですが、旦那に相談すると、「うーん、まだ決めるのは早いんじゃないかな?」と、言葉を濁されて決まりませんでした。どうやら私が考えた名前ではなくて、自分で決めたかったようです。
実家の親は何も言ってきませんでしたが、旦那の両親は同居もしているせいか、色々言ってきました。意見がまとまらずに、結局は旦那も、「赤ちゃんが産まれてから、顔を見て決めよう!」と言うので、そうすることにしました。
旦那自身は、旦那の父親の会社の上司がお寺の住職だったので、その人に名前をつけてもらいました。なので、赤ちゃんが産まれたら、その住職さんの姓名判断で、名前の候補を挙げてもらうことにしました。
10個ほど挙げてもらったのですが、そこからも旦那の親と旦那で意見が割れていて、産まれてから1週間も悩みました。
私は字画が良い名前が良かったので、挙げられた候補を姓名判断で調べて、一番運勢の良い名前を主張しました。最終的には、旦那が「出産を頑張ってくれたから」と言って、私の意見に決めてくれました。
2人目のときも、やはり同じように住職さんに候補を聞いて、私が字画でより良いものを探しました。このときは、みんなの意見が合ったのですぐに決まりましたが、読み方をどうするかで迷いました。最後は旦那の意見に合わせました。
3人目のときは、旦那と義母さんが同じ意見だったのですが、長男・次男が大きくなって、子供たちが強く主張をしてきました。次男はずっと、「ぴよちゃんがいい!」と言い張っていましたが、それはさすがに却下しました(笑)
でも、長男は譲らずに旦那と張り合っていましたが、最後には旦那が折れて、長男の意見に決まりました。
こんな感じで、最終的にはわりと旦那が折れてくれました。なので、1人目なら赤ちゃんが生まれてから考えると、旦那が出産の苦労をわかってくれて、納得できる名前を付けさせてくれるかもしれませんよ。
回答9:最初に譲れない条件を1つずつ決めておく

むつみ(1982年生まれ/子供1人/認定産後ドゥーラ)です。我が家は両親・義両親は初めから名づけには関わらない方針だったので、夫婦で決めました。ですが、私も夫も優柔不断な性格なので、「きっとやみくもに名前を探しても決めきれないよね」と、最初にお互いの「譲れない条件」を1つずつ決めました。それが、
- 名字と合わせた画数が良い名前にする
- 小学校一年生でも読み書きでける漢字にする
でした。そして、育児情報誌の企画でもらった「名字に合う名前ベスト10」という冊子の中から条件に合った5候補を選んで、ひとつずつ突き合わせて勝ち抜き戦をしていく、という選び方をしました。
そんな選び方をしていたある日、それまで候補になかった名前が私の頭に降ってきました。しかも、最初に決めた条件に一番合っていて、名字と合わせた響きも良いのです。「どうして最初からそれが候補に挙がらなかったんだろうね?」とお互い不思議に思ったほどピッタリでした。
一応、勝ち抜き戦の候補として入れ直しましたが、その名前があっさり生き残ることになりました。きっと私の思い付きだけでは生き残らなかったと思います。
結局は、「先に条件を決めていたこと」が、我が家で大きく揉めなかったコツです。私たちの意図した通り、息子はどこでも誰にでも間違われずに名前を読んでもらえるので、良い名づけができたなぁと感じています。
回答10:旦那にすべて任せるべきたったひとつの理由

はらだひな(1988年生まれ/子供2人/身内に助産師)です。私の場合、旦那に名付けを頼んだので、旦那と意見が合わないことはありませんでした。
でも、両親からは意見があったので、それに対しては「参考にしとく」と言っていました。最初は私自身も名前を考えていましたが、子供が生まれたあとに旦那に「親としての自覚」を持たせて、育児に参加させたい希望があったので、「子供を無事に産む責任を私が持つから、あなたは名付けの責任を持って」と言いました。
名付けを私や両親などが考えてしまうと、旦那がまだお腹の中にいる子供への関わりが少なくなってしまって、子供に対する関心も無くなってしまうと思ったからです。まだお腹の中にいる子供に対して、名付けを考えるのは旦那にとって初めての「親になる実感」が得られると思いました。
両親も「◯◯(旦那)が名付けするなら」と納得してくれたので、我が家では揉めたり面倒なことは無かったです。もし、両親から名付けで何か言われても、「旦那に任せてあるから」「旦那にも子供に対する責任感持たせたいから」「旦那が一生懸命考えてるから」と、言いきっちゃいます。
結局、名付けを旦那に頼んで正解でした。旦那は子供に関心を持ってくれていますし、「良い名前だね」なんて子供が褒められると、旦那も嬉しそうです。名付けで揉めるのも面倒なので、思い切って旦那さんに任せちゃってもいいかもしれないですよ。
回答11:「絶対にやめて」と言っていたはずの夫の案を採用した話

あきママ(1983年生まれ/子供5人/双子出産)です。我が家では子供の名づけは夫婦で考えることができて、他の家族も私たちの意見を尊重してくれました。
もともと、私と主人は真反対の性格です。「きっと名づけも意見が合わないだろうな」と思って、最初からどちらかが名前(呼び方)を考えて、どちらかはそのあとの漢字を考えることにしました。母親である私が呼びやすい名前を考えて、そこから主人が漢字を考えることにしました。
分担していたのにも関わらず、主人が考えてくれた漢字に意見してしまって、主人を困らせてしまったことが多々ありました。特に、長男の名づけには主人が「◯◯(私)の名前の漢字を一文字使いたい」と言ってくれたのですが、私は大反対でした。
「親の名前の漢字を受け継ぐと、親を超えることはできない」「子供がずっと親に依存してしまう」と聞いたことがあったので、「絶対やめてほしい」とお願いしていました。でも、主人に理由を聞いてみるととても感激してしまって(笑)、その字を使うことにしました。
主人が私の字を「使いたい」と言ってくれていた理由は、
- 私がいなければ長男も生まれてきていなかった
- 私の名前を考えてくれた両親に対して、今までの感謝の気持ちを込めて絶対に一文字は使わせてもらいたい
- 母親と同じ字を使っていることに意識を持って、ずっと私の支えになってほしい
という考えからでした。
私の子供たちはみんな、漢字を考えるところで主人と意見が対立しました。ですが、主人の考えを聞いてみると、「主人の意見に合わせたほうが子供にとっていい名前になるな」と、折れる部分が出てきました。
なので、絶対に自分の意見を押し通したい部分もあると思いますが、まずは相手の理由をしっかりと聞いてみてください。
回答12:両親には自分たちの思いを伝えれば理解してくれる

ぴよママ(1987年生まれ/子供2人/保育教諭)です。名付けは楽しみな反面、「これだ!」という名前に出会えるまで悩みますよね。私の1人目の妊娠中は義父母との同居中だったため、女の子とわかってからは義母が名前の候補を次々と紙に書いて持ってきました。これぞありがた迷惑です(笑)感謝の気持ちよりも「ほっといてくれ」という思いでした。
そこで、主人からさりげなく「赤ちゃんのためにありがとう。でも、親である僕たち2人が考えた名前を産まれてくる子どもにはつけてあげたい」と伝えてもらいました。すると、義母も口を出すことはほとんどなくなりましたよ。思いを伝えれば理解してくれるものです。
それからは、夫婦2人で「たまひよ」の名付け本や携帯で名前を調べました。字画や字数、名字との相性を確認して、お互い紙に名前の候補をすべて書き出しました。
また、「男の子なら主人が、女の子なら私が、最終的に赤ちゃんの名前を決定する」というルールを最初に決めていました。同姓同士だからという簡単な理由です(笑)
話し合いを重ねた結果、1人目は主人と私の使いたい漢字を一文字ずつ組み合わせた名前をつけました。2人目はあえてひらがなで名前を考えてから、あとで漢字を当てはめていく方法で名前を決めました。
結果として、2人とも「名前は古風だけど、漢字は今風」という満足いく名付けができました。名前を最終決定する時も、揉めることはほとんどなかったです。
というわけで、両親には「自分たちだけで名前を付けたい」という思いを伝えて、そこからは2人だけのルールを最初に決めて、夫婦で話し合いながら名付けをしてみてください。
↓妊娠後期の人は、この記事も人気です!

トップページに戻る:葉酸サプリクラブ – サプリメントアドバイザーが辛口で評価