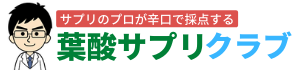回答7:お金の計算が苦手な主婦でもできる4つの貯金方法

ヨカっち(1976年生まれ/子供4人/自宅出産)です。確かに、将来の学費は高そうで、私も心配です。でも、私は細かいお金の計算が苦手で、今まですべてザックリやってきました・・・。
なので、「○年後には○万円貯金を作る」とかは具体的に考えたことがないです。その上、毎日コツコツ節約するのも息苦しくて苦手です。まったくふざけた主婦なのですが、私なりに実践した貯金方法を4つご紹介します。
1.学資保険
まず、学資保険です。1人目だけソニー生命の「5年ごと利差配当付」に入りました。年払い97,620円で、18歳満期時には200万円支払われます。実際の積立額(1,757,160円)より多く支払われるので、どこよりもお得感があって選びました。
でも、保険に入ったのは家計的にその1人だけです。2~4人目では、上の子の幼稚園で月4万円人かかって、徐々に生活費も増えたので入れませんでした。
2.子ども名義の口座にお祝い金やお年玉を貯める
一方、全員必ずしたのは、子ども本人名義の口座にお祝い金やお年玉を貯めることです。出産、七五三、入園、入学祝い、毎年のお年玉など、その子宛にもらっているのを当人の口座に入れています。
お祝い返しなどの経費はなるべく家計から出して、もらった分はほぼ全額貯金です。下の2人は市から出産奨励金30万円が出たので、それも入れました。この貯金が学費の第1候補です。
3.財形貯蓄
多目的貯金として「財形貯蓄」をやっています。毎月25,000円ダンナの給料から自動的に天引きされるので、「最初からないもの」という感覚で貯められています。普段は忘れているので、気付くとまとまった額が貯まっていていいですよ。定期預金と違って、申請すれば好きなときに下ろせます。
4.住宅ローンの借り換え
ムダをなくすために2年前に住宅ローンの借り換えをしました。金利が購入時の1/3になっていたので、月々2万円ちょっと返済額が減りました。手数料など50万かかりましたが、残り25年もあったので十分ペイできます。この浮いた2万円も、生活費とは別の口座で貯金しています。
こんな感じで、周りと同じレベルの生活をしながら貯蓄もある程度できています。でも、6年後には保険に入れていない2人目が高校生です。「これだけじゃ絶対足りないな」と正直恐いです。
でも、「大学はムリ!」と今から完全に諦めているわけでもありません。これから私がいくら稼げるか、ダンナの昇給が望めるか、にもよりますし。
将来、子供にやりたいことをやらせてあげたいのは当然です。でも、レジャーに行ったり、習い事をさせたり、子供たちの「今」も同じくらい大切です。その中で、子供が興味を広げて大学以外の道を発見するかもしれないし、未来は未知数です。
ウチはダンナも同じ考え方です。毎月できる範囲の貯蓄はしているので、消費とのバランスはとりあえずこれでいくつもりです。
私も相談者さんと同じく、「子供が小さいうちは自分がしっかりお世話したい」と、1人目出産から専業主婦をしてきました。ところが、現在は末っ子が幼稚園年中組になって、「そろそろしっかり稼がないとな」と思いつつも、腰が重いです(苦笑)
妊娠中から学費の心配をされている相談者さんは、私よりずっと計画的な人です。計画が早ければ貯まるのも早いと思いますので、あとは自分に合ったやりかたを見つけるだけだと思いますよ!
回答8:意外!ファイナンシャルプランナーのおすすめは生命保険

むつみ(1982年生まれ/子供1人/認定産後ドゥーラ)です。我が家は妊娠した時に、迷わず「教育資金と言えば、やっぱり学資保険でしょ!」と思ったのですが、いざ選び始めると保険会社によって色々なプランがありすぎて、どれがいいのかわかりませんでした(笑)
そこで、CMでよく見かけていた「保険見直し本舗」に行きました。色々な会社の保険の情報を持っていて、いま加入している保険を見直したり、相談者の状況に合わせて保険プランを組み立ててもらえるカウンターです。他に「ほけんの窓口」なども見かけますが、一番近いという理由で「保険見直し本舗」に行きました。
ファイナンシャルプランナーの方に色々な案を提示してもらった結果、私たちは学資保険ではなくて、「メットライフ生命」の終身タイプの生命保険を選びました。
提示されたときは、「生命保険をどうやって教育資金にするの?」とびっくりしたのですが、「生命保険を掛けながら、解約返戻金を大学以降の教育資金に充てる」という提案でした。
夫の死亡保障・障害補償も付きながら、約15年後の解約返戻金が払込金額の100%を上回ります。その頃に息子が大学入学予定なので、そこで解約すれば大学資金に充てられます。もし、一人目の子どもで解約しなければ、保険を継続してさらに大きくなった返戻金を二人目の資金にすることもできます。2人目でも使わなければ老後の費用に・・・。
15年後の解約返戻金は300万円くらいなので、他に見比べた学資保険の満期時と大きく変わらない金額です。でも、使い方に自由が利く点が良いと思って選びました。
自分で書き出すだけではわからなかったり行き詰ったりしますし、知らない情報もたくさんあります。そういった意味でも、専門家であるファイナンシャルプランナーさんに診てもらうのはオススメです。
回答9:まずは習い事を優先。大きくなってから資金計画を立てる

はらだひな(1988年生まれ/子供2人/身内に助産師)です。私は、毎月の子供手当てを保険を使って貯蓄しています。
子供が3歳になるまではオムツなど消耗品のお金がかかると思って、子供手当て15,000円のうち5,000円を消耗品にあてて、残りの10,000円を貯めています。子供手当てが終わるのが15歳で、高校進学にお金が必要なので、満期を15歳にしました。
保険は、最初の2年は返戻率の高いソニー生命の学資保険にしていましたが、2人目が生まれてからは保険を見直しました。2人分を一気に貯めるほうが返戻率が高いので、「メットライフ生命」の15年払い込み終身保険に私名義で入りました。上の子が高校入学くらいに満期となって、1人200万ちょっとずつ貯まるプランにしました。
私が万が一のときに保険金が700万円降りるし、私の生命保険は大した内容の保険ではなかったで、「万が一」も考えた上で選び直しました。
今のところ、「高校進学」に向けての貯金しかしていません。「大学進学」に向けての貯金は、上の子が小学生になったタイミングで、毎月払ってた保育料25,000円分を貯金にあてるために、新たに保険に入って貯める予定です。
そうすれば、大学進学のときに270万円ほど用意できます。下の子の大学進学の貯金は、上の子の貯金状況によって考えようと思っているので未定です。
我が家は、子供がしたいこと(習い事)をまずはさせてあげて、そこから資金計画を立てます。上の子は現在4歳ですが、スイミングやサッカー、こどもチャレンジなど習い事をしているので、毎月かかるお金としては保育園料25,000円、習い事15,000円、洋服代など雑費も含めると毎月50,000円近くお金がかかってます。
下の子は2歳で、習い事はまだ始めてませんが、保育園料が32,000円(兄弟割り有りなら16,000円)、オムツ代5,000円、その他の雑費含めて毎月40,000~50,000円かかります。
なので、十分と言えるほど貯金ができてないですが、小さいうちから習い事をしておくのは、後々いい影響があるとも思ってるので、まあいいかなって考えです。小さいうちは何かとお金がかかるので、子供にかかる生活費をだいたい把握してから、教育資金を計画するのが良いと思います。
回答10:学資保険入ってたら、保険任せで済むから楽チンよー

もこママ(1984年生まれ/子供4人&双子出産)です。私は二人目が産まれてから、農業協同組合の学資保険に加入しました。
それまでは「これは家の分」「これは子供の分」「これは学資保険」といくつも口座を作ってそれぞれ貯金していたのですが、二人目が産まれてから、管理する口座が増えてわけがわからなくなってしまいました。
そんなときに、私が利用している保険の担当者さんから学資保険の話を聞いて、「これなら教育資金は保険任せで済んで楽になる!」と思って、加入しました。今は4人とも学資保険に加入しています。
18歳の満期時に大学の入学金が貯まって、満期以外でも小学校、中学校、高校入学のタイミングで引き出せるプランにしました。制服も高いし、通学で自転車を使用する場合は自転車がいるし、他に何かとまとまったお金がいると聞くので、家計からではなく保険の貯蓄から出せるようにするためです。
とりあえず毎月掛け金を払っていれば貯まるので、口座を一つずつ管理していた頃よりずいぶん楽になりました。また、学資保険に加入して良かったのが、教育資金の予定と金額の目安がわかることです。
自分で貯めていたときは実際どれくらい貯めれば良いのかわからなかったし、本当に貯められるのか不安でした。でも、保険の担当者さんから「目安はこれくらい」「そのためには掛け金これくらい」「そうするとこのときはこれくらい貯まってる」と教えてもらえました。
無知だった私は、「やはり資金繰りはプロに任せて良かったなあ」と思いました。ママ友と話すとき、みんな悩みは一緒で「この先、どれくらいお金かかるんだろう?」という話になることがあります。そんなときは「学資保険入ってたら、保険任せで済むから楽チンよー」と話しています。
回答11:できることから節約・貯金して、家計簿アプリ「Zaim」で管理

ぴよママ(1987年生まれ/子供2人/保育教諭)です。子どもの将来のためにどのくらいのお金を貯めればいいのか‥‥不安になりますよね。私も結婚前は趣味や買い物に自由にお金を使っていたので、最初はお金をどうやって貯めていったらいいのかわからずに悩みました。現在は、次の4つの方法に落ち着いています。
1.学資保険(かんぽ生命)に加入
まずやってみたことは、主人の義父が郵便局員だったので、ゆうちょ銀行の学資保険(かんぽ生命)に入りました。中学、高校、大学の入学時にそれぞれ80万、100万、200万などまとまったお金が入ります。
月々の支払いは長男が15.000円、長女が13,000円ぐらいです。男の子のほうが将来は家庭を守っていかなければいけないので、しっかり一人前に育ってほしいという思いで少し高めの保険に入りました。
2.夫婦の生命保険の見直し
私たち夫婦の生命保険(かんぽ生命)の見直しをしました。最初はワンランク上のプランに加入していたのですが、子どもが産まれてからは掛け金を1万円ほど落として、夫婦合わせて月12,000円ほどにしました。満期を迎えると主人は100万、私は80万返ってくる保険です。
3.財形貯蓄
義父のアドバイスで「財形貯蓄」をしています。銀行の自動積立で、毎月決まった金額が給料から引かれて貯金できる方法です。我が家では毎月20,000円に設定していますが、必要な時に使うこともできるし、「いつの間にか貯まっている!」という感覚なので、無理なく将来のために貯蓄できています。
4.児童手当の全額貯金
産まれてすぐに子ども達の通帳をそれぞれ作って、お年玉や児童手当は手をつけずに全額貯金しています。児童手当は娘が4歳、息子か2歳なので、毎月10,000円と15,000円、合わせて4ヶ月に一回10万円支給されます。
というわけで、我が家では「できることからコツコツと」をモットーに、今必要なお金を計算・把握して、節約したり、少しずつ貯金しています。「Zaim」というアプリを使えば家計簿も簡単につけられますので、ぜひ使ってみてください。
回答12:学資保険は解約。パルシステムの出資金を利用
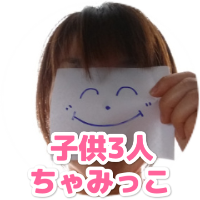
ちゃみっこ(1976年生まれ/子供3人/調理師)です。教育資金、私も不安です。子供の進路はその時になってみないとわかりませんが、「大学に行きたい」と言うなら、親として気持ちに答えてあげたいと思うのは当然ですよね。
うちの場合、1人目2人目は子供が産まれてすぐに1人月額13,000円の日本生命の学資保険に加入しました。ですが、幼稚園に入園してから保育料などお金がかかり始めて、生活が不安定になってしまったため、解約しました。今は、旦那の職場で毎月2万円の積み立てをしているのと、児童手当てをなるべく使わないでいます。
あとは、パルシステムの会員なので、毎月出資金をして、少しずつ貯めています。パルシステムの出資金は、幼稚園の入園準備や、学校の入学準備のときに、まとめて下ろしています。貯まっている額が数万円であっても相当助かります。
正直、これらだけでは将来の高校や大学の授業料には全然足りていないと思います。一番下の子が、まだ幼稚園の満三歳クラスなので、もう少し大きくなったら、仕事をしてさらに貯蓄額を増やそうと思っています。
↓妊娠後期の人は、この記事も人気です!

トップページに戻る:葉酸サプリクラブ – サプリメントアドバイザーが辛口で評価