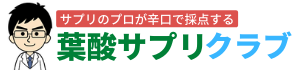今回は、子どもの教育資金の貯め方について、相談にお答えします。

●今回の相談
もうすく臨月になるので仕事を続けることがつらくなって、勤めていた会社を退職しました。そのため、私の収入は一切ありません。出産後2~3年は育児に専念したいので私は働けないです。
今のところ主人の収入だけで問題なく生活ができているのですが、子どもを育てるためにどのくらいのお金がかかるのかよくわからずに、不安に思っています。
できれば子どもには大学まで行ってほしいと思っています。でも、そこまでの教育費が貯められるのか、「このままの貯金のペースで大丈夫なんだろうか」と不安です。子供の教育資金はどのように貯めていますか?(妊娠35週目、29歳、りんちゃん)
回答1:教育資金の予定表を作って計画的に貯金する

カナミ(1984年生まれ/子供3人/図書館司書)です。私も結婚と同時に会社を退職して、今年3人目を出産したばかりです。しかも、転勤族なので、まだ働けていません。
よく世間では「子供1人を大学まで行かせるには1,000万円必要」と言われていますよね。初めて聞いたときは、「うちは子供が3人いるし、3,000万必要なの?!」と焦りました。ごく普通の一般家庭の我が家では、宝くじでも当たらない限り、急にそこまで資産を増やせないのが現状です。
そこで私が実践してみたのが、「必要な資金の予定表を作ってみる」ことでした。例えば、我が家ですと、現在5歳の長女がいて、1年後には公立小学校に入学します。周りのママ友に聞いたり自分で調べたところ、「入学費用はランドセル含めて15万円くらいあればいい」とのことでした。
なので、まずは小学校入学までに入学資金15万円を用意しておきます。同時期に、次女は幼稚園に通園している予定ですので、長女の小学校の給食費などの費用を合わせると、だいたいその年に必要な教育資金がわかります。
こうして1年ごとに想定される金額をシミュレーションして、その年までに必要な額を用意しておくようにしています。

↑これが実際の資金予定表です。Excelで作りました。
もちろん、必ずしも親が思う進路を進むわけではないと思います。ですが、「もしこの子が私立大学に進んだら……」と仮定して、具体的に試算してみると、「この年までに○○万円貯めておこう」と必要な金額のイメージがしやすいです。私はこれで漠然とした不安がなくなりました。
資金の予定表を作ってみたことで、「今すぐに1人につき1,000万円貯めなくてもいい」と、改めて気づけました。なので、予定表でお金の動きを把握して、貯蓄の貯めどきを知って、少しずつ貯金できるように計画を立ててみてください。
回答2:仕事復帰までは児童手当を子ども専用の口座に貯金しておく

すずこママ(1980年生まれ/子供3人/元看護師&保健師)です。子どもにかかるお金も大学まで出す場合では、とんでもなくお金がかかると世間では言われていますよね。我が家も子どもが3人いますので、将来のことを考えると胃が痛くなります(笑)
私も2人目の出産後に保育園の空きがなくて退職しました。現在は3人目を出産して半年経ちますが、夫だけのお給料で何とか生活できています。私自身も大学まで出してもらっているので、子どもたちの教育資金はきちんと貯めておきたい考えです。夫とも定期的に相談・見直しをしながら貯蓄しています。
1人目は1歳から保育園に通っていて保育料も高額(3歳未満児の頃は48,000円)だったので、毎月の児童手当を貯金するだけにしていました。児童手当は、3歳まで15,000円で、以降は10,000円です。
保育料は、小学校入学と同時にアフラックの学資保険へシフトチェンジしました。毎月の貯蓄金額が27,000円と高めで、10歳までに支払いが完了するタイプを選びました。早めに支払期間が満了していれば、いずれ2人目、3人目ができても負担にならないことを見込んでのプランでした。
現在、2~3人目の子どもたちは、児童手当だけをそれぞれ子ども専用の口座に貯金しているだけです。私も来年から仕事が決まりましたので、働いてから学資保険や他の貯蓄方法も考えていく予定です。
我が家の方針としては、生活資金が大幅に変わることのないように無理なく貯蓄することを目標にしています。生活水準を落としてまで貯蓄にお金は回したくないですからね。
学資保険などは毎年新しい商品が出ますので、その時その時でいいものを選ぶしかありませんし、児童手当も制度が変われば金額の変動もあるので、一概にあてにしてはいけないと思っています。
大切なのは、少しずつでも一定の金額を毎月コツコツ貯蓄することです。そのお金は絶対に生活資金に使わないこと、生活に影響が出ない金額であることが鉄則です。そのためには、「児童手当の積み立て」が一番確実な方法です。
子どもが小さいうちは働けないかもしれませんが、いずれ働くことをビジョンに入れての貯蓄だけで十分だと思いますよ。
回答3:家計は切り詰めないで、児童手当だけ貯めておく

まこ(1984年生まれ/子供2人&元看護師)です。我が家は残念ながら夫の収入だけではカツカツなので、産後すぐにライターとしての仕事を再開して、家計を助けています。
子どもたちがまだ生後6か月、1歳10か月と幼いため、「今は無理に仕事を増やさないで、できる範囲で貯めていこう」と思って、家計からの貯蓄ではなくて、子どもたちの児童手当を、そのまま教育費のための貯蓄としています。
現在、児童手当は3歳未満まで月額1万5千円、3歳以上中学3年生まで月額1万円支給されます。まったく手をつけずに貯めれば、高校入学までに子ども一人あたり約200万円貯めることができます。
なので、児童手当は専用の口座を作って、その口座には一切手を付けないように家計をやりくりすることで、教育資金の貯蓄を行っています。
今は0歳児から通える英語教室や、ベネッセなどの通信教育、公文のベビークラスなどがあるため、「赤ちゃんの間は教育費が一切かからない」とは言い切れません。我が家も現在、ベネッセの「こどもチャレンジ」を受講しているため、受講費が月約5,000円かかっています。
一方で、最近話題の「幼児教育無償化」が現実となれば、月2万円以上はかかる私立幼稚園(公立幼稚園なら、自己負担額はもっと少ないかもしれません)の費用負担がなくなるかもしれません。
よって、教育資金は「どれくらい貯めれば安心」というものでもありませんし、逆に、子どもが乳幼児の段階では、「最終的に教育へこれだけかかる」という試算もしにくいです。
出産後2~3年は育児に専念したいなら、家計を切り詰めてまで教育費を貯めないことです。まずは、我が家のように「児童手当は手を付けずに貯めておく」といった無理のない範囲から始めてみてください。
回答4:月5,000円で良いので、学資保険に加入しておく

こじかママ(1985年生まれ/子供3人/看護師)です。私は今まで3つの県で子育てをしてきましたが、地方自治体によって学校・保育園の料金や、助成金、給食費、学費、医療費が全く違うので、今でも教育資金には悩みます。
私は、両親のすすめで「かんぽ」の学資保険に入りました。学資保険は、大学入学の時にお金が入る保険です。子どもが小さいときから積み立てをしておけば、月々の支払う保険料も安くなります。私は1人5,000円程度の支払いで、3人分で月15,000円ほど支払っています。18歳でそれぞれ100万円を受け取れるプランにしています。
妊娠中からも積み立てができますし、支払い義務のある人を父親にしておくと、何らかの事情で死亡してしまった場合でも、月々の保険料を支払わずに、大学入学時期にもらうはずだったお金をもらえます。また、息子が入院したときには、日額2,500円ほどの入院費用をもらえました。これは本当にありがたかったです。
我が家は、一番上の子が小学生で、来年は2番目の子も小学生になります。いよいよ本気でお金が不足してきそうなので、今まで専業主婦をしていましたが、今年の10月に看護師として仕事復帰しました。
今はパートで6時間勤務ですが、あと2年後はみんな小学生です。小学生になったら働き方を変えて、収入を増やして、新たに学資保険のような、積み立てもできて、保険の効力もあるような貯金をしていきたいと考えています。
なので、ぜひ「学資保険」に加入してみることをおすすめします!
回答5:私が児童手当を貯蓄にまわさない理由

あきママ(1983年生まれ/子供5人/双子出産)です。私が教育資金として貯めているのは大学進学のための資金ですが、上の子4人は「ソニー生命」の学資保険に加入しています。学資保険に入る際、「月々の負担もそれほどかからなくて、無理なく18歳の満期まで続けられる額で」と考えていました。
自宅から通える地元の国立大学の1年の学費が約60万円で、4年間では約240万円かかるので、子供1人当たり200万円受け取ることができる保険に入っています。4人分で月4万円弱支払っています。
一方、下の子は保険に入っていません。うちは主人が自営業をしていますので、退職金目的の「逓増定期保険」に入っています。逓増定期保険では、下の子が19歳になるときに満期を迎えて、退職金として一定額受け取ることができます。大学入学よりも少し早い時期に受け取れば、下の子はわざわざ学資保険に入らなくても大丈夫かなと考えています。
貯蓄しているのは大学進学の費用だけなので、義務教育でも修学旅行や、宿泊体験、高校入学などまとまったお金がいるときが来ます。日々の生活費をやりくりして貯蓄をしているので、そこから捻出していく予定です。
ちなみに、児童手当は1人目、2人目はそれぞれ月5000円、3人目以降は月1,5000円を受け取っています。最初は児童手当を貯蓄しようと考えていたのですが、小さいうちに色々な経験をさせてあげたいので、児童手当の金額内で習い事をさせています。
自分の好きなこと、得意なことを一緒に見つけてあげることは大切だと思うので、無駄遣いではないと考えています。
というわけで、今はご主人の収入だけで生活できる状況なら、無理のない金額だけ貯蓄にまわしてみてください。お子さんが大きくなって、再び働くことができるようになってから貯蓄額を増やせばいいと思います。今は、お金には代えられない、お子さんと過ごす時間もぜひ大切にしてください。
回答6:毎月の生活費の上限を決めて、超えないように節約する

カッチ(1983年生まれ/子供1人/元看護師&韓国在住)です。我が家は、「月にいくら」と決めて貯蓄をしていませんし、保険にも入っていません。その代わりに、「育児手当には手を出さない」ことと、「生活費を節約する」ことを実行しています。
育児手当は、0歳のときに月2万円、1歳で1万5千円、2歳になると1万円になります。保育園に預けると、育児手当はもらえなくなる代わりに保育量を国が全額負担してくれます。
娘を2歳になる前に保育園に入れたので、育児手当は2万円を12ヵ月間、1万5千円を9ヵ月間受給できました。そのお金は、娘の病院費以外には使わないようにしました。毎月病院に通ったり、入院していたので、受給金すべてが貯まったわけではありませんが、まとまったお金にはなりました。
2歳を過ぎて受給がなくなってからは、医療費にも使わずそのまま置いてあります。これから娘のために必要な出費が起こったときに使おうと思っています。
また、生活費を月2万5千円と決めています。外食を含む食費、日用品、レジャー費など、医療費以外の生活に必要な費用すべてです。ちなみに、韓国の物価は日本とほぼ変りません。
特にお金がかかるのは、外食とレジャー費です。外食は月に1~2回に減らしました。また、週末娘を遊ばせる場所は、無料で利用できる遊び場や子ども博物館をみつけて、1ヵ月後の予約をしておきます。無料の場所は予約を取りにくいので、あらかじめ予約をしておきます。
以上のように、我が家では具体的に目標金額を決めて貯金していません。生活費以外のお金は旦那が管理しているので、実際にどのくらいの貯金があるのかも把握していません。それでも、節約は間接的に貯金になると思います。