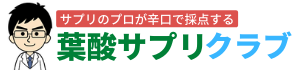今回は、妻が妊娠したのに父親になる自覚のない旦那について、実体験ベースで相談にお答えします。
●今回の相談
妊娠が発覚したとき、旦那は「少し早すぎた。もう少し2人だけの新婚生活を楽しみたかった」と言い放ちました。その時点で多少の不安は感じていたのですが、共働きなのに家事を手伝う様子もなくて、仕事が終わって帰宅すると自室にこもってゲームばかりやっています。
また、私につわりの症状が出てつらそうにしている時も、「大丈夫?」と声掛けはしてくれるものの、積極的に家事を手伝ってくれる様子がありません。そして、妊婦健診の時に赤ちゃんの様子を話したり、エコー写真を見せても、「ふーん」と聞き流す程度であまり興味を持ってくれません。
このような旦那でも、赤ちゃんが生まれたあとは、私や子供と向き合ってしっかり父親として育児に参加してくれるものでしょうか?(妊娠25週目、31歳)

体験談1:旦那が変わるのを待つのではなくて、積極的に育児をやらせる

なな(1989年生まれ/子供2人/元婦人科看護師)です。私が学生のとき母性の授業で、「父親は子供が生まれてからではないと、父性が芽生えない」と先生から聞いたことがありました。
なので、私の旦那には、「私は妊娠しているから『母親になるんだなぁ』と思っているけど、父性って難しいよね?意識して父親になろうと思わなくても大丈夫だから」とよく言っていました。旦那も「お腹は大きくなっているけど、生まれて抱っこしない限り、実感しないかも」と言っていました。
私は妊娠して身体は大変になっていくのに、家事はいつもと変わらない量をこなしていました。旦那も遊びに行く回数を制限することもなくて、ごく普通に過ごしていました。
旦那に聞かれてなくてもエコーの写真を見せたり、「今これが大変」だとか、「赤ちゃんこんなに体重増えた」だとか細かく報告をしていました。うち旦那も「ふーん」と聞き流す程度でした。
でも、産婦人科の両親学級で出産のシーンを見たとき、父性がちょっと芽生えてきました。旦那に「生まれてからオムツ替えとかお風呂とか教えてよ?たぶんさ、不器用でイライラすると思うけど、怒らないで教えてよ」と初めて言われました!

出産後は、とにかく旦那がいるときには積極的に育児をやらせました。もちろん自分がやったほうが早いのですが、その甲斐もあってようやくしっかり父親と自覚して、私が言わなくてもいろいろやってくれるようになっていました。
というわけで、旦那が変わってくれるのを待つのではなくて、旦那がいるときに育児をいろいろやらせて変わらせるのが良いです。妊娠中は、ちょっと我慢して旦那さんに思う存分遊んでもらってください。妊娠中に「父親としての自覚が……」とか考えなくても大丈夫ですよ。
体験談2:夫が自分から子どもと関わってくれる時期を待って

すずこママ(1980年生まれ/子供3人/元看護師&保健師)です。私の夫も1人目の娘を妊娠したときはそれほど喜んでくれなかったので、不安なお気持ちよくわかります。
私も当時は共働きで、家のことは99%私がやっていたのもあって、夫にはとてもイライラしてばかりの毎日でした。娘が産まれてからも、あまり積極的な育児参加はしてくれませんでした。初めての育児で大変だったのもあって、私は実家にいることが多かったです。
確かに、男性は直接お腹の中の赤ちゃんを感じることができないので、父親としての自覚が芽生えにくいのもわかります。
私は父親としての自覚を早く持ってほしい気持ちもあって、読みやすそうな育児書を買って夫の机の上に置いてみたり、インターネットや育児雑誌で、関心の少ない夫に対してどうしたらいいか調べてみたりしたものの、何一つ効果的なものはありませんでした。
最終的に私が辿り着いた方法は、育児参加を強要しないで、夫が自分から子どもと関わってくれるようになる時期を待つことにしました。娘がよく笑うようになってきた頃に、ようやく夫も「子どもの相手をするのが楽しいと思えるようになった」と話していました。
それからは、お風呂も入れてくれるし、時々寝かしつけもしてくれるようになりました。今でも自室でパソコンやスマホばかりいじってますが、「こういうときは手伝ってほしい」「こういう状況のときは子どもを見ていてほしい」など、具体的に夫に伝えています。
そうすることで、やっと私の気持ちもわかってくれるようになってきたかなと感じています。どうしてもイライラが募ると感情的になって喧嘩になり兼ねないので、できるだけ落ち着いて冷静に、「これだけはわかってほしいこと」を厳選して伝えるようにしています。
ということで、私は3人目にして、ようやく夫の扱い方が上手くなりました(笑)なので、ご主人に過大な期待はしないで、ご主人の気持ちが育つまで気長に待ってみてください。
体験談3:無関心だった夫が、超イクメンパパになった2つのポイント

まこ(1984年生まれ/子供2人&元看護師)です。私は一人目の妊娠がわかったとき、夫から「おめでとう」を他人事のように言われたのを、約3年が経った今でも忘れることができません。女性はずっと、こういった言葉は忘れることができないものですよね……。
そんな夫でしたが、今ではどんなに仕事で疲れていても、帰宅後すぐに子どもたちの食事の世話から、歯磨き、お風呂、寝かしつけまで全て私と一緒にやってくれる、超イクメンパパに成長しました!夫が変わったポイントは次の2つです。
ポイント1:子どもが生まれてようやく実感が湧いた
夫いわく、「お腹の中に自分の子どもがいるって言われても、男は実感がわかないんだよね。生まれてきてくれてはじめて、あぁ自分は父親になったんだなと思ったし、親として一緒に育児をしなくちゃと思った」とのこと。
なので、妊娠中は関心がないように見えても、お子さんが生まれてから実感が出て、育児や家事を手伝ってくれるかもしれません。
ポイント2:里帰りをしないで2人で頑張った
夫がイクメンになった理由としてもう一つ考えられるのが、「里帰りをしないで、一番大変な時期を二人で乗り切った」ことです。私の実家は遠方で、祖父の介護中でした。夫の実家は、義父が介護を受けている状態なので、産後でも一切頼ることができませんでした。
そのため、退院後は夫と二人で、慣れない子育てと向き合う必要がありました。夜中も2時間置きに授乳しなくてはならくて、ふらふらな私を見て、夫は「僕がいる間は少しでも休んで」と優しく声をかけてくれました。慣れないオムツ交換やミルクを積極的にやってくれるようになりました。
また、休日に子どもと2人きりでいると、なかなか家事をする時間が取れない私の状況も察してくれました。「子どもがいるんだもん。家事なんてできなくても僕は構わないよ」と言ってくれるようになりました。
結局のところ、男性はとにかく「実際に体験しないとわからない」ことが多いです。今後イクメンになってもらうためにも、ぜひ出産後はどんどん育児や家事を体験するように、女性側からアプローチしてみてください。そうすることで、たとえ今は興味を持ってくれなくても、少しずつ変わってきてくれるはずです!
体験談4:父親として合格ラインに達するまで6年かかった失敗談

ヨカっち(1976年生まれ/子供4人/自宅出産)です。私のダンナも、相談者さんのダンナさんとほぼ同じタイプの人です。心中お察しいたします。
経験から言いますと、「手伝ってほしい」などの要求は面倒でも口で伝える必要があります。そして、結果はかなり長い目で見る必要があります。ウチの場合は、私が「父親としてまぁOK」と思えるようになるまで、1人目出産から6年くらいかかりました。
現在はだいぶ自発的になってくれましたが、それでも子育てに積極的な周りのパパには到底及びません。ですが、彼なりに頑張ってくれているのを理解したので、私もあまり気にならなくなりました。
ウチのダンナは、妊娠中はもとより、産後も赤ちゃんに対して愛情が自然に芽生えなかったようです。新生児の我が子を見て、「サルみてーだな」という感想でした。最初は私も「父性は、お世話する中でそのうち湧いてくるだろう」とノンビリ考えていました。
でも、いつになっても頼まないと手伝ってくれなくて、不満が募っていきました。それから子供が1歳半になったころ、「やっとかわいくなってきた」と驚きの発言。「え!じゃあ今までかわいくなかったの?」とショックでした。
その2年後には、自分の趣味のイベントのために幼稚園行事をパスしようとする始末。これにはさすがに「そんなに子供に興味ないわけ!?」と怒鳴ってしまいました。普段ほとんどキレない私の剣幕に、やっと自分の立場を自覚したようでした。
それで私もわかったのですが、どうやら彼は「いつまでたってもコドモ」な人だったのです。「あなたはもうパパなんだから、これからは自分だけじゃなく子供のことも考えて」とこちらで教えてあげないといけなかったみたいです。
というわけで、今思えば、私は我慢しすぎたと思います。相談者さんはそうならないよう、早めの対策をオススメします。次の3つが大切です。
- 自分で背負い込まずに、口や態度で「パパ手伝って」と伝えること
- 自分の理想のパパ像をダンナに求めないこと
- 長い目でみること
特に、理想は捨てたほうがいいです。不要なストレスを抱えてしまいますから。
でも、忘れないでいたいのは「パパとして行動が未熟でも、もちろん愛情はある」ということです。かけがえのない自分の子供ですからね。彼なりのパパっぷりを受け入れつつ、こちらの意思を伝えていけば、徐々にうまくいくと思いますよ。
体験談5:赤ちゃんだけでなくて、夫をイクメンに育てる努力も必要

あきママ(1983年生まれ/子供5人/双子出産)です。まるでうちの主人を見ているようで、不安な気持ちがよくわかります。
12年前に初めて妊娠がわかったとき、主人は喜んでくれたものの家事を手伝ってくれたり、一緒に妊婦健診に行ってくれたりすることはありませんでした。妊婦健診について来てくれたのは、「帝王切開の説明があるので、ご主人を連れてきてください」と言われたときくらいです。
「きっと赤ちゃんが生まれたら変わってくれる」・・・と思っていましたが、産後も主人の仕事が忙しくて、家事育児を手伝ってくれることはほとんどありませんでした。「手伝ってほしい」とお願いすると、嫌な顔をされたり、何かに理由をつけて断られてしまいます。
なので、私も「もう自分でやるしかない」と、何もかも自分でやるようになっていました。そのせいで、父親になる自覚が出る環境を作ってあげられなかったことも、よくなかったなと思っています。
今は主人が家にいる時間が増えてきたので、子供たちと過ごしていく中で、父親としてできることをやろうとはしているみたいです。でも、今まで一緒にいた時間が少なかったせいか、色々と空回りしてしまうことが多くて、あとで私がダメ出しをしています。子どもと一緒に主人も父親として成長している段階です。
男の人は、奥さんが妊娠していても自分の体に変化はないです。なので、「父親になるんだな」という感覚はなかなか育ちにくいはずです。赤ちゃんが生まれたあとに子供とのかかわりを持てば持つほど、父親として成長していくものなんだろうなと思います。
ということで、産後も今の状況と変わらなかったら、ご主人の変化を待たないで、ご主人が育児に関わることのできる状況を作ってあげてください。「自分でやってしまったほうが早い」と思う場面でも、ご主人に最後まで任せてみると、きっと父親としての自覚を持つことにつながるはずです。
「赤ちゃんを育てていくと同時に、ご主人をイクメンに育てている」という気持ちで、赤ちゃんとパパとの時間を見守ってあげてください。
体験談6:赤ちゃんが生まれてからも変わらなかった夫を変えた方法

むつみ(1982年生まれ/子供1人/認定産後ドゥーラ)です。我が家も新婚時期の妊娠だったので、「待望の赤ちゃん」と言うほどではありませんでした。夫は無関心ではないものの、戸惑っている感じでした。
妊婦検診に積極的に付いてきてほしかったのですが、混雑する土曜日の検診を嫌がって、初めの頃は自分の予定を優先して付いてきてくれませんでした。家事も私からお願いしなければ、自分の担当分だけ済ませておしまい・・・という状態でしたね。
赤ちゃんが豆つぶ大のエコー写真を見せたりしても、こちらが期待していたほどの感動が見られなくて、「彼にとって自分ゴトじゃないんだ……」とがっかりした記憶があります。
そんな夫が少しずつ変わってきたのが、妊娠30週ごろでした。私のお腹のふくらみがはっきり目立ってきて、エコー写真が人の形になって、胎動も外から触ってわかるようになったころです。私の会社の帰りに駅まで迎えに来てくれたり、自分から負担の大きい家事をやってくれるようになったんです。
私は「お父さんになってくれた!もう大丈夫」とすっかり安心したのですが、赤ちゃんが生まれてからからの育児参加は以前とあまり変わらなかったので、とてもがっかりしました。里帰り出産だったので、家族で生活するまでに3か月ほど時間があったのが原因かもしれません。
そのあとは、おむつ替えのような小さなことから夫を巻き込んで、実体験してもらいながら一緒に子育てをするようにしました。すると、夫は「最初は何からやればいいかがわからなくて不安だった。小さな経験を一緒に積めていけたから、だんだんと父親として自覚を持てるようになった」と言っていました。
なので、「子どもができれば私が母になっているように、夫も自然と父になってくれるだろう」という期待はしないほうがいいです。一緒に子育てを体感することで、父親の自覚が芽生えてくるものだと思いました。
体験談7:夫に約束事(役割)を与えたら変わってくれた

ぴよママ(1987年生まれ/子供2人/保育教諭)です。私たち夫婦も、入籍してすぐに妊娠が発覚しました。結婚式を挙げるときには妊娠3ヶ月で、新婚生活をじっくりと味わう間もなく母親と父親になりました。
主人は趣味の多い人なので、妊娠前も妊娠中も私のことは放置(笑)で、釣りやパチンコ、バスケやダーツなどに平気で出かけていました。
内心は何もしない夫にイライラしましたが、逆に私も「1人の時間を楽しんでやる!」と開きなおって時間がある時は1人カフェに行ったり、買い物したりして赤ちゃんのためにもストレスを抱え込まないようにしていました。
そんな毎日が続くなか、「もっと父親になる自覚を持ってほしい」と思って、いくつか約束事を決めました。例えば、赤ちゃんが産まれるまではゴミ出しと風呂洗いは主人にしてもらいました。そして、赤ちゃんが産まれたら「お風呂入れはパパの仕事」と決めていました。
このように2人で話し合って、旦那さんには仕事(役割)を与えるといいですよ。そして、何かしてもらった時には「ありがと~助かるぅ~(はーと)」と、オーバーリアクションで褒めて褒めて褒めまくることも大切です(笑)
すると、主人も悪い気はしなかったのか「これしようか?」と自分から率先してやってくれるようになりましたよ。赤ちゃんが産まれてからは、自分の趣味に使う時間よりも家族といる時間を大切にしてくれるようになりました。
今では2人の父親として頑張ってくれています。家事などはほとんど手伝ってくれませんが、子どもたちと遊んだり、絵本を読んでくれたりするだけでも十分だと思うようになりました。
結局のところ、旦那さんも私の旦那と同じように「何をしていいのかわからない」だけかもしれません。やってほしいことや、思いをきちん伝えて話し合えば大丈夫だと思います。かけがえのない子どものためですから。過度な期待はしすぎずに、夫婦で協力して子育てを乗り越えていってください。
体験談8:立会い出産で子どもを抱っこした瞬間に、父親の自覚が芽生えた

はらだひな(1988年生まれ/子供2人/身内に助産師)です。まず、まだ産まれてないのに、「父親としての自覚」を持ってる人に私は会ったことがありません。父親として自覚が生まれ成長するのは、赤ちゃんが産まれてからだと思います。
私の主人は、1人目が産まれるまで「亭主関白」でした。私もフルタイムで仕事してるのに、家事は全部私ひとり。つわりで辛いときも、心配はしてくれても家事は「俺の仕事じゃない」と言って、パチンコに出かけたりする始末。毎日ムカつきました(笑)
それに、「俺、父親になる自覚ない。いつになったら自覚持てるんだろう?」と、本人が言ってたくらいです。ただお腹が大きくなるのを見たり、エコー写真だけじゃ「他人事」と思ってる感じでした。
父親として自覚を持たせる、関心を持たせるために、私は名付けを主人に任せました。これから産まれてくる子供のことを、生涯の名前を考えることが「自覚を持たせる一つの方法」だと思って、妊娠初期から考えてもらいました。


でも、主人の行動は変わらず「亭主関白」でした。名付けを任せて、子供に関心を持たせたはずが、「俺は今どきのイクメンにはなれない」と言われました。なんなら、「立ち会い出産も絶対しない」とも言われて、その時に私は「育児は私ひとりでやっていこう」と思ったほどです。

ですが、1人目の出産時のハプニングで、助産師さんたちに無理矢理立ち会い出産をさせられて、産まれて間もないわが子を「怖い怖い」と言いながらも抱っこした瞬間に、主人はやっと「父親になった」と実感したそうです。

主人の顔に似ているからか、とても嬉しそうな表情をしてたのを私は今でも覚えてます。
それからは、入院中も里帰り中も毎日子どもを見に来てくれました。抱っこしたり、子供と接する時間が増えるほど、私から何かを言わなくても家事や育児をしてくれるようになりました。周りの人たちは、主人の子煩悩ぶりにビックリしていました(笑)
結局のところ、お腹の中にいるときと、産まれて実際に関わることとでは、関心や父親としての自覚は違ってきます。私の周りのママ友や知り合いでも、産まれてから協力的になってくれた父親が多かったです。なので、今は関心が無くても、産まれて子供に関わる時間を持たせることで、父親としての自覚を持って協力的になってくれるはずです。
体験談9:健診で先生に「パパ」を使って説明してもらうと効果バツグン

もこママ(1984年生まれ/子供4人&双子出産)です。まさにうちの主人と同じです。私たちはできちゃった結婚だったので、心の準備がありませんでした。なかなか父親の自覚がわかなくて、どうしたらいいものかと私も悩みました。
そんなとき、一人で定期健診に行くと、夫婦で健診を受けに来ている人の会話を耳にしました。「めっちゃ動いてたなぁ」「顔は隠してたな」と、先ほど撮ったであろうエコー写真を一緒に見ながら会話をしていました。
「ああ!これだ!」と思って、帰ってから主人に「次の健診ついてきて!なんかお父さんも一緒に来る日らしい」と訳のわからない嘘をついて(笑)、ついてきてもらうことにしました。エコーも診察も一緒に見てもらうと、主人は「おお……」とか「あっ」とかですが、やはり目の前で動いている赤ちゃんを見ると興味が湧いたようです。
そして、一番効いたのが先生が発する「パパ」の言葉でした。「今日はパパも来てくれたのねー」「この鼻筋辺りはパパ似かなー」「男の子だし、パパにたくさん遊んでもらおうねー」などなど、先生が「パパ」を連発してくれました。
診察にも入ってもらって、私が「最近おなかが張ることがたまにあります」と告げると、先生は「おなかが張ったら休んでね。家事もパパが手伝えるところは手伝ってあげてね。手伝えなかったらママがさぼってても許してあげてねー、入院になると大変だからねー」と、主人にもあれこれ話してくれました。
おかげで、それから意識が変わったようで、エコー写真を愛でるように見てみたり(笑)、私の体調も気にしてくれるようになりました。
というわけで、健診について来てもらったときは、先生に「パパ」という言葉を使って説明してもらえないか、先生に相談してみてください。第三者に「パパ」と呼ばれると、意識も変わると思いますよ。
体験談10:そっけなかった旦那が育児に参加し始めたきっかけ
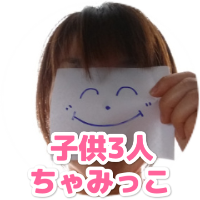
ちゃみっこ(1976年生まれ/子供3人/調理師)です。せっかく赤ちゃんを授かったのに、旦那との気持ちのすれ違いが起きてしまうと不安になりますよね。うちの場合は、1人目のときは旦那もすごく喜んでくれたのですが、2人目、3人目を妊娠したとき全く興味を持ってくれなくて、何もかも私1人で頑張っていました。
旦那からすると、1人目のときは「初めてで大変」という認識があったものの、2人目からは、「もう育児経験があるのだから、自分で何でもできるでしょ」という感覚だったようです。旦那の親と同居しているので、旦那がやらなくても親が手伝ってくれるというのも、旦那が動かなくなる原因だった気がします。
特にひどかったのが3人目の出産のときです。陣痛促進剤を使っての計画出産だったので、出産日は事前にわかっていました。ですが、旦那は仕事が休めなくて、私1人で出産をしました。赤ちゃんが産まれたあと、仕事が終わって急いで駆けつけてきたものの、「産まれたんだ?ふーん」とそっけない感じでした。
赤ちゃんも少し抱っこしただけで感動もあまりなくて、「上の子たち連れに行ってくる」と、すぐに立ち去ってしまいました。その態度には看護師さんたちも「ずいぶんそっけない旦那さんねぇ」と、ヒソヒソ話していました。
正直、そのそっけなさは子供が2才くらいになるまで続きました。それでも、「沐浴だけはパパの仕事!」と言って、やってもらっていました。それが良かったみたいで、2才すぎて言葉も増えてきた頃から、急に可愛がり始めたのです。
私が家事をしている間や用事があるときに、外に連れて行ったり、面倒を見てくれるようになりました。オムツ替えまでやってくれたのには本当にビックリです。旦那いわく、「今までは子供に話しかけても反応があまりなかったから、実感が沸かなかった。けど、言葉が増えて会話ができるようになって、すごく可愛く思えてきた」とのことでした。
父親はお腹の中から一緒にいる母親と違って、自分の子供という実感がなかなかつかめないのだと思います。実感が掴めるまでは、なかなか妻が思う通りには動いてくれないかもしれません。
それでも、沐浴など何でもいいから「パパの仕事」と決めて手伝ってもらうことで、後々実感が沸きやすくなると思いました。旦那が本当のパパになるまで、気長に待ってみてください。
妊娠したのに父親になる自覚のない旦那にイライラする人は、妊娠中期・後期向けの葉酸サプリ「プレミン14w」の内容も気になっています。