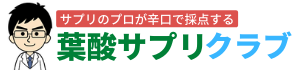今回は、離乳食をアレルギー対策で開始時期を遅らせても大丈夫なのか。離乳食の進め方の真相に実体験ベースでお答えします。
●今回の相談
私は食べ物のアレルギーは特に持っていません。ですが、主人が白身魚やフルーツ全般に対してアレルギーを持っていて、少しでも食べるとかゆくなったり、肌が赤くなったりします。
主人がアレルギー持ちなので、子供までアレルギーになることが怖くて、離乳食はとても神経質に考えてしまっています。
そのため、離乳食を始めるタイミングを7ヶ月に入ってからと通常よりも遅くしてしまいました。まだ今の段階ではおかゆ以外のものには挑戦していません。
このままゆっくりペースで離乳食を進めていっても大丈夫ですか?それとも、ちゃんと時期に沿ったものを食べさせるようにしたほうが良いのでしょうか?(産後7ヶ月目、27歳、まっさん)
体験談1:保育園を利用するなら、開始時期が遅いと後悔するかも

まこ(1984年生まれ/子供2人&元看護師)です。ご主人に食物アレルギーがあるとなると、お子さんにも遺伝していないか不安になってしまう気持ちはわかります。
ですが現在、「アレルギーを起こしやすい食事は遅らせるのではなくて、むしろ早くから少しずつ摂取させることでアレルギーを起こさない確率が高くなる」という研究結果もあります。(参考:子どもの食物アレルギー 新しい対策|NHK健康ch)
また、保育園を利用する場合も要注意です。「離乳食はゆっくりで良い」という考えから、1歳を過ぎてもまだ摂取できるメニューが少ないままだと、保育園に入ってからすごく苦労してしまいます。
わたしは5か月から離乳食を進めたので、1歳児になった時点で幼児食へスムーズに移行できました。ですが、離乳食のペースを遅らせてゆっくり取り組んでいたママ友は、入園後に「なぜ1歳過ぎなのにこんなに離乳食が進んでいないの?」と保育士から指導を受けていました。
離乳食が完了するまでずっとお弁当を作らなくてはならなくて、「もっと早くから進めておけばよかった」と後悔していました。
もちろん、わたしが知らないだけで、ゆっくりしたペースで進めるメリットもあるとは思います。ママ友が離乳食を遅らせた理由は、「アレルギー対策もあるし、母乳がよく出ていたから、少しでも長くたくさん飲んでもらいたかったから」と話していました。
でも、私は通常通り離乳食を進めたことで、上の子は1歳で幼児食へスムーズに移行&離乳完了となりました。そのおかげで、お出かけもしやすくなって、子どもも夜ぐっすり寝られるようになって、生活リズムを整えやすくなりました。
ということで、現在は5か月から少しずつ離乳食を始めることが奨励されていることを考えると、今から遅れを挽回するために、アレルギー専門医のアドバイスを受けながら、時期にあったものを食べさせたほうが良いのではないかと思います。
体験談2:西原式を実践した経験から言うと「全く問題なし!」
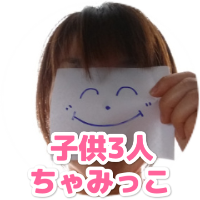
ちゃみっこ(1976年生まれ/子供3人/調理師)です。うちも相談者様と同じく、私はアレルギー持っていないのですが、旦那の家系がアレルギー体質です。「アレルギーは遺伝する」と聞いたので、とても心配でした。
そんな中、実家の姉から、「西原式離乳食の進め方」というのを教えてもらいました。「離乳食開始を通常より遅くすると、アレルギーになりにくくなる」というものでした。
たんぱく質は普通、お腹に入ったあと消化器官にで消化されて、小さなアミノ酸にまで分解されてから体に吸収されます。ですが、赤ちゃんはまだ腸の発達が未熟で、腸壁がざるのように荒いため、たんぱく質が分解される前の大きい粒のまま体に吸収されてしまいます。
大きいたんぱく質は体にとって未知の存在であるため、敵とみなして攻撃して、アレルギー反応が起こる・・・というのが西原式の考え方です。
腸が離乳食を受け入れられるようになるのは、2歳くらいからだそうです。実際、江戸時代は2歳すぎまで母乳のみで育てていたそうです。なので、西原式では離乳食は2歳すぎてからを推奨しています。
でも、離乳食を遅らせると、ちゃんと栄養が摂れているのか、成長が遅れていないか、とても心配になりますよね。相談者様は7ヵ月で始めたとのことですが、西原式を実践した私からしたら全然早いほうだと思います。うちの長男は1歳まで母乳オンリーでしたよ!姉の娘なんて1歳3ヵ月まで母乳のみでした。
当時は離乳食を遅らせている人は周りにいなくて、義母やママ友からの風当たりは強かったです。「本当に大丈夫なの?離乳食始めたほうがいいよ」何人の人から言われたことでしょう。心が折れかけたことも何度もありました。
でも、当時7歳の姉の娘は何の問題もなく育っていたし、姉からも助言を受けて、自信を持って続けることができました。
肝心の我が子の結果ですが、長男はそれでも軽度の卵アレルギーが出てしまいました。ですが、重度のアレルギー・アトピー体質である旦那の家系を考えると、軽く済んだのは頑張ったおかげかなと思っています。2人目、3人目は見事にアレルギーは出ませんでした!
離乳食の開始を遅らせた分、母乳の質には気をつけていました。母乳だけで育てる以上、母乳に栄養がなければ発達に関わるからです。アレルギーは母乳からも移行するため、なるへくアレルギーになりやすいものは食べないで、ビタミン・ミネラルを多く摂るようにしていました。
このことを理解してくれる病院にかかるのが一番ですが、近くにない場合でも乳児健診で順調に育っていれば問題ないと思います。
また親バカな話ですが、うちの子供たちみな、キュッと引き締まった筋肉で、運動が大得意な子に育ちました。背も高いですし、幼稚園や学校でもリーダーシップを発揮しています。とても発達が遅れているとは思えません。西原式の先生が言っていたとおりの結果になりました!
というわけで、7ヵ月から離乳でも、乳児健診で問題なければ全く心配いりませんよ!自信を持って育児しましょうね。
体験談3:長男が8半熟卵でアレルギー症状を起こて学んだこと

ヨカっち(1976年生まれ/子供4人/自宅出産)です。ウチは、夫婦とも食物アレルギーがなかったので、気にせずにセオリー通り離乳食を進めることができました。嫌がったり、食べが悪かったりしたことはありましたが、1歳半にはだいたい普通の食事ができるようになりました。
離乳食の進めかたについては、私は早すぎても遅すぎても赤ちゃんには負担だと思いました。いつまでも母乳やミルクで成長してはいけないので、やはり少しずつでもセオリーに近づけていく努力が必要だと思います。
ちなみに、ウチは長男が8歳になって初めて半熟卵でアレルギー症状を起こしました(それまで、卵は好きではないけど、普通に食べていました)。
咳から始まって、徐々に呼吸が苦しくなっていったのですが、夕食後のことで医者に行くべきか相当悩みました。幸い、2時間ほどで症状が和らいだので、受診はその日にはしませんでした。
その後、病院でアレルギー値を調べてもらったのですが、卵の数値は卵白が4.2UA/mLで、卵黄は0.7UA/mLでした(←全然大したことないレベル)。
お医者さんが言うには、「必ずしも数値と症状は一致しない」そうです。また、「呼吸困難になりかけていたのでは、その日に受診しないと危険ですよ!」と怒られてしまいました(汗)「運がよかったんだぁ……」と思って、ゾッとしました。
なので、離乳食では、初めてのものは少しずつ与えて、すぐ医者にかかれるよう午前中にしておくこと、夜間にかかれる医者をチェックしておくことは大切だと思いました。
アレルギー検査もとりあえず受けてみると良いと思います。もちろん、ウチの長男のように数値に表れないとか、逆に数値が高いのに本人はけろっとしている(長男はスギ花粉の数値が580UA/mLもありますが、症状は普通の鼻炎程度で、薬も使用しません)とかのケースもあるので、当てにしすぎない程度にです。
ニュースでもアレルギーによる深刻な事例を聞くことがありますし、周りにもアレルギー持ちのお子さんは当たり前にいます。ママが食事やおやつを日常的に気にしてあげているのを見ると、感服してしまいます。
やはり、アレルギー対策は家族の努力しかないのだなと思います。最初は勇気がいるでしょうが、お子さんの成長のため、がんばって乗り越えてくださいね。
体験談4:保育園の調理師さんのアドバイスで考え方が変わった

ぴよママ(1987年生まれ/子供2人/保育教諭)です。アレルギーに対して神経質になってしまう気持ちわかります。私は保育園で働いているので、別メニューでアレルギー食を食べている子どもたちの苦労や、お母さんたちの悩みも知っています。
私も1人目を産んだばかりの時、「我が子はアレルギー体質にしたくない」と、色々ネットで調べました。特に、おかゆの時期が終わった6ヶ月頃からは、「卵」や「乳製品」「肉類」「魚類」など普段調理でよく使う物に敏感になって、使うのをためらっていました。
そこで、保育園の調理師さんに相談したところ「まずは一口ずつでいいからやってみないと、アレルギーがあるかないかわからないよ」「アレルギーにビクビクするより、赤ちゃんの成長や時期に合った食材を使って、食べ物のおいしさを伝えてあげてほしい」と言われて、その言葉が心に響きました。
それからは、少しずつ色々な食材を離乳食に取り入れてみることにしました。例えば、牛乳を数滴おかずに混ぜてみたり、卵の白身をあげてみて様子見。臆病な性格なので、黄身をあげるのにまた数日かかりました(笑)
あと、地域の保育園の子育て支援イベント「離乳食の試食会」にも参加してみました。「こんな食材も使えるんだー」と調理の幅も広がって、とても勉強になりましたよ。
赤ちゃんは新しい味にとても嬉しそうで、よく食べてくれるし、悩んでいた時に比べて私自身も楽しく離乳食が作れるようになりましたよ。今2人の子どもがいますが、2人ともアレルギーもなく元気に育っています。
ちなみに、保育園にいる子の中には、赤ちゃんの頃はアレルギー体質だったけど、年齢を重ねるたびにアレルギーの食材が減っている子や、全てなくなった子もいます。
「同じ物ばかり食べさせすぎると、アレルギー体質になってしまう子もいる」と聞いたことがあるので、同じ食材にかたよったメニューにならなければ大丈夫だと思いますよ。もちろん、初めて食べた離乳食のあとは、しっかりと赤ちゃんの状態を観察してあげてくださいね。
体験談5:アレルゲンになりやすい食材以外はどんどん食べさせるべき

カッチ(1983年生まれ/子供1人/元看護師&韓国在住)です。離乳食を始める時期は、お母さんたちの間でも賛否両論ですし、赤ちゃんが食事に関心を持つか持たないかによっても違います。私のまわりにも4ヵ月から始めた人もいますし、6ヵ月ごろから始めた人もいます。
私の娘は、4ヵ月から下の前歯が生え始めて、大人が食事をしているのをジーっと見るようになりました。なので、「これは離乳食を始めるタイミングなのでは?」と思って、実家に帰省するタイミングでもあった5ヵ月目から始めてみました。
私には食物アレルギーはありませんが、食物アレルギーが心配ではあったので、アレルゲンとなりやすい食材はなるべく遅めに与えるようにしていました。
なので、牛乳・卵・肉類(鶏肉以外)は1歳を過ぎてから、キウイ・パイナップル・マンゴー・ピーナッツ・豆乳などは未だに与えていません。
キウイは、保育園で一度出たのですが、胸の辺りに発疹ができました。病院へ行くと「アレルギーの可能性がある」と言われたので、それ以来は食べさていません。
マンゴーは、乾燥マンゴーを食べられるので大丈夫だと思いますが、生マンゴーはまだ与えていません。小麦粉は1歳前にうどんが大丈夫だったので、大丈夫と判断して食べさせました。鯖も1歳ころに食べて大丈夫でした。
7ヶ月を過ぎると、さつまいも・かぼちゃのペースト・ほうれん草・ブロッコリー・にんじん・りんごなどを混ぜながら離乳食をつくりました。それ以外は市販の離乳食(粉をお湯に溶くだけ)を使っていました。市販の離乳食にはアレルゲンになりやすい食材は入っていないので、安心して食べさせられますし、手抜きもできます(笑)
離乳食の目的は、食事のたのしさや色んな味の体験をさせることだと思っています。アレルギーを怖がっておかゆだけあげていると、赤ちゃんが食事や食べ物に関心を持たなくなるかもしれません。
また、咀嚼・嚥下(えんか=飲み込むこと)・消化の訓練の意味もあります。娘は、同じペーストでも、繊維の多いほうれん草やかぼちゃはうまく飲み込めませんでした。でも、段階を踏むうちに上手に飲み込めるようになりました。おかゆの固さを変えるだけでは不十分だと思います。
というわけで、アレルゲンになりやすい食材は決まっていますので、それ以外はどんどん離乳食に取り入れて良いと思います。そして、1歳前後からアレルゲンになりやすい食品も少しずつ取り入れて、はじめて食べさせるときは「平日の午前中に」という原則を守れば、怖いことはないですよ。
体験談6:離乳食を遅くするのは悪くない。助産師に相談した友人の話

むつみ(1982年生まれ/子供1人/認定産後ドゥーラ)です。アレルギーを持っている家族がいると、どんな症状が出るかもわかりますし、かわいそうで子どもには同じ思いをさせたくないお気持ちはとてもわかります。
離乳食を遅くすることは悪くないと思います。離乳食は物を食べる練習の期間です。それは、栄養を取るだけでなくて、口の動かし方、飲み込み方の練習も含んでいます。栄養は母乳やミルクからも十分取ることができますから、栄養面は心配しすぎなくても大丈夫です。
私の息子は乳糖不耐症になったので、5か月目から離乳食をスタートせざるを得ませんでした。ですが、アレルギーや食事の準備を考えると、できれば6か月からスタートしたかったです。
私の友人のお子さんは、お兄ちゃんに卵アレルギーがあるので、次のお子さんには卵を食べさせる時期を遅らせています。他に、アレルギーではありませんが、赤ちゃんがドロドロの食感のものを嫌がって、全く離乳食を食べてくれなくなってしまった友人もいます。
その友人は、1歳近くになって固形のものが食べられるようになるまで、離乳食を延期したそうです。助産師さんにも相談したら、「母乳が飲めればそれで大丈夫。」と言われたそうです。
離乳食のペースはその子によってさまざまです。いずれアレルゲンへのチャレンジは必要になりますが、育児書は参考程度に、お子さんの様子を見ながら進めてあげてください。お母さんと赤ちゃんが安心して楽しくごはんを食べられることが、一番の離乳食の練習です。
体験談7:息子に卵と牛乳アレルギーが出た!そのときかかりつけの先生は・・・

なな(1989年生まれ/子供2人/元婦人科看護師)です。私も主人も食物アレルギーは特にありませんが、息子は離乳食期に牛乳と卵でアレルギーが出ました。5カ月で離乳食を始めたのですが、7カ月の後半で卵の黄身をあげていて、少し量を増やしたときに出ました。牛乳は、1歳を過ぎたとき少量あげたら出てしまいました。
アレルギーに神経質になるのはわかります。私も息子が卵でアレルギーが出たとき、「離乳食をやめてしまいたい」とすら思いました。ですが、かかりつけの先生が「アレルギーが出たからってやめちゃったら、そのままずっとアレルギー。少しずつでもあげていけば、アレルギー出なくなるから」と言われました。
そう言われても、子供のアレルギー反応は過剰なので、とても心配でした。食べてから、だんだん身体をかき始めて、まぶたが蜂に刺されたように腫れて、全身蕁麻疹が出て、身体がとても熱くなって、だるそうな顔をします。一度「呼吸が止まったらどうしよう……」と不安になって、夜間救急に受診したこともあります。
でも、何度相談しても、かかりつけの先生は「大丈夫。子供はちょっと敏感なだけ。ほんと少しずつでいいから、あげて。血液検査しちゃうと心配になるだけだから」と言われたので、検査もしませんでした。
先生からは卵ボーロを少しずつあげることを勧められたので、卵黄のみ使用の卵ボーロをあげていました。すると、1歳になる前には全卵も食べられるようになっていました。牛乳も、少しずつ量を増やしてあげ続けたらなくなっていました。
アレルギー、怖いですよね。でも、離乳食を進めてあげてください。アレルギーの出た物でも、あげていれば、私の息子のようにだんだんアレルギーの反応がなくなっていくことがほとんどだそうです。むしろ、大きくなってからでは難しいそうです。
もちろん、アレルギーが出たら先生に相談してください。今はしっかり食べられるようにしてあげないと、必要な栄養が摂れないので、頑張ってください。
体験談8:ゆっくりでいいから、おかゆ以外の食べ物に挑戦して

あきママ(1983年生まれ/子供5人/双子出産)です。我が家は兄弟5人とも5か月になったら離乳食をスタートさせました。
離乳食のスタート時期は、長男のころの育児雑誌には「5か月ごろから」、四男のころは「あまり早い時期からの離乳食はおすすめできない」とか書かれてあって、「はたして、5か月からスタートさせるのがいいのか悪いのか・・・」と考えていました。
でも、家族にアレルギーを持っているものがいなかったので、気にせず色んな食べ物に挑戦していました。もちろん、「もしかするとこの子だけ・・・」ということも考えられたので、赤みのあるお肉やお魚はいきなりたくさんの量を与えることはしませんでした。
徐々に量や回数を増やすことで、もし体調が悪くなったらアレルギーの原因になるものがわかりやすいかなと思ったからです。
同じものを与え続けていては、その食べ物を飽きてしまう可能性が出てきます。おかゆってエネルギーになる大切な食べ物ですから、おかゆを食べなくなるといけませんよね。
ちなみに、うちの子供たちには、「みんなで一緒にご飯を食べているんだよ」と赤ちゃんの段階から感じてもらいたかったので、家族の食事時間に一緒に食卓に座らせて離乳食を食べさせるようにしていました。
7ヶ月は歯も生えてくるころで、少し食べ物を噛む練習も必要になってくる時期です。おかゆは柔らかいので、あごの力をつけることができません。
結局のところ、離乳食のスタートが遅かったのなら、離乳食の完了も少し遅くなると考えておくと良いと思います。あせって急に固い物を食べてしまっていては、きっと赤ちゃんも食べることを嫌がってくると思うし、何より体調面でよくありません。
今から少しずつ、ゆっくりのペースでよいので、おかゆから次の段階へステップアップしてみてください。
体験談9:アレルギーが心配だからこそ色々な食材に挑戦すべき

はらだひな(1988年生まれ/子供2人/身内に助産師)です。自分の子供の検診の際に、まさに同じような悩みを持つお母さんが、保健師さんに相談していました。
「離乳食を遅らせると、成長とともに必要な栄養が摂れなくて成長に影響が出る場合もあるので、できるだけ時期に沿ってあげて」といった話をしていました。
私の場合は、2人とも離乳食の開始は5ヶ月ごろからでしたが、アレルギーの反応が出やすい小麦や卵などは、万が一アレルギー症状が出ても良いように、病院の受診へ行ける時間に食べさせていました。それに、1歳過ぎてから保育園へ預ける予定だったので、できるだけ保育園へ通うまでに多くの食材を食べさせるようにもしました。
生後7ヶ月ということですが、ゴックンが上手にできるのであれば、徐々に色々な食材に挑戦したほうが良いと思います。離乳食ってわりと作るのが面倒ですが、初めての食材をあげる時の子供の反応がわりと面白かったりします。
アレルギーは心配ですが、アレルギーが心配だからこそ色々な食材に挑戦すべきだと思います。ただ、そこは親のペースではなくて、あくまで子供のペースに合わせてです。順調に離乳食が進めれると良いですね。
体験談10:離乳食の進み具合がとても遅かったうちの子の場合

もこママ(1984年生まれ/子供4人&双子出産)です。うちの場合はアレルギーは特に気にしなかったのですが、離乳食の進み具合がとても遅くて、途中で産院の先生や保健師さんに相談しながら進めました。
離乳食は、5か月になったときにおもゆからスタートしました。おもゆがお粥になり、野菜スープを飲ませたり、検診で教えてもらった通りの進め方をしていましたが、なかなか固形物(舌でつぶせる柔らかさ)に進めませんでした。
市販のベビーフードなども活用しましたが、固形物は口に入れても吐き出してしまって、そのうち今まで食べてくれていたおかゆも食べてくれなくなりました・・・。すでに8か月になっていましたが、まだ初期段階から進めていない状態です。
産院の検診時に相談したところ、「気が乗らないなら無理に進めないで、食べれるものを食べさせてあげて。でも、食べさせることをやめないで。毎食同じメニューでも良いから、栄養は二の次でも良いから、食べることに興味を持たせて、『食事は楽しいことだ』っていうのは教えてあげられるようにしてね」と言われました。
そんな中、かろうじて食べてくれていたのが、バナナを潰したものと、初期の子が食べるベビーフードのバナナプリンでした。「毎食バナナとバナナプリンじゃなあ……」と悩みましたが、とりあえず食べてくれるものを食べさせました。
10か月ごろ、ふと私が食べていた白ご飯に興味をもった様子だったので、少し食べさせてみるとおいしそうに食べてくれました。まだ10か月で普通の白ご飯は早いのですが、保健師さんに聞いてみると、「おなかも壊さず食べてくれるのなら、少量ずつ食べさせてあげて」と言われて、そのころから一気に食べるものが増えました。
結局、うちの場合は離乳食の中期を飛ばして、いきなり後期で、完了食になりました。育児書通りにはいかなくても、その時が来たら食べてくれるんだなと思いました。
なので、アレルギーが気になる場合は私なら病院にその旨を話して、アレルギー検査をしてもらうことからスタートします。その結果を知った上で、焦らずに離乳食を進めていくのが良いのではと思います。
↓授乳中の人は、この記事も人気です!

トップページに戻る:葉酸サプリクラブ – サプリメントアドバイザーが辛口で評価