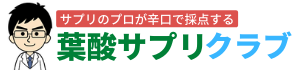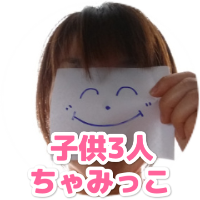今回は、「産後クライシスを乗り越えたい」という相談に、実体験ベースでお答えします。
●今回の相談
出産を機に、生活のスタイルが変わりました。赤ちゃんはかわいいのですが、慣れない育児に悪戦苦闘しています。寝たいときに眠れない。食べたいときに食べられない。赤ちゃんとは会話が成立しないので、なぜ泣いているのかわからないなど、肉体的にも精神的にも疲れてしまっています。
私が仕事を辞めたこともあって、家事は私一人で行なっています。夫は、出産前から家事には協力的ではありません。子供が生まれてからも、帰宅時間が遅いこともあって家事も育児も手伝ってくれません。
そのせいか、夫婦の会話も減ってしまいました。むしろ、夫からのちょっとした一言でイライラしてしまう自分がいて、同じ屋根の下で暮らしているのも苦痛な状態です。
友人にも相談したのですが、「いつも買い物などの外出でも、子供と夫と一緒に仲良く出かけているけど」との話を聞いて、涙が出てきました。正直、夫への愛情がなくなっています。産後、このような気持ちになった場合、どのようにして乗り越えたら良いのでしょうか。
(産後3ヶ月目、美奈子、32歳)
回答1:産後クライシスを乗り越えるポイントは2つ
ウチのダンナも、子育てに参加してくれませんでした。いつまでも自分ペースの生活をして、なかなか親の自覚も持たないままでした。当然、イライラしました。それで、お互い険悪なムードになって「この人とずっとうまくやれるだろうか」と思ったりもしました。この危機を乗り越えられたのは、次の2つのことがポイントでした。
1.一時的な感情で行動しなかった
本当に頭にきていても、数日~数週間やりすごします。すると、少し冷静になれるんです。感情がピークのときに「離婚」がよぎったとしても、時間を置くと「シングルになったらどんな生活か」を具体的に考えられました。それで「ちょっと厳しいな」と思って、ダンナへの不満を我慢することがメリットに感じられました。
もちろん、そんな打算的な考え以外にも、「ちゃんと話し合ってみよう」とポジティブな考えが生まれたりもします。
2.自分だけ我慢しっぱなしじゃなくて、やってほしいことを口に出し続けた
ダンナは言われて初めて行動してくれる、超絶気の利かない人でしたが、今はだいぶ私の希望にそった父親になって来ています。それでも、ときどきは不満がありますが、過度な期待をしないのも習慣になったので、気にならなくなりました。
相談者さんのダンナさんも、「すぐにパパになれない人」なんだと思います。「どうせやってくれない」と諦めずに、部下でも育てる感じで、「おむつ替えて」「泣いてるから抱っこしてあげて」と具体的な指示を出すようにしてみてください。
結局、ママは子供と一緒にパパも育てる必要があります。赤ちゃんのためには、シングルマザーより円満夫婦のほうが絶対にいいはずです。長い目で見て、クライシスを乗り越えてください。
回答2:赤ちゃんを連れて外出してみる
「産後3ヶ月」というと、そろそろ赤ちゃんの首もすわってきて、お出かけができるようになる時期です。そこで、気分転換を兼ねて、赤ちゃんと2人でお出かけしてみることをおすすめします。
赤ちゃんと一緒だと、ミルクやおむつなど持って行くものがたくさんあるので、外出を躊躇しがちですが、短時間でもお出かけするだけで、精神的にとても元気になりますよ!
私も妊娠をきっかけに、病院での看護師勤めを辞めて、在宅仕事へ切り替えました。産後すぐは慣れない育児に手一杯だったのですが、生後3ヶ月ごろになると、肉体的、精神的な限界を感じるようになりました。
そんなとき、たまたま自分の使い捨てコンタクトがなくなりそうだったので、思い切って赤ちゃんを連れて買い物に出かけました。たった1時間程度の外出だったのに、帰ってきたら精神的にとてもスッキリしていて、それまで感じていたイライラがかなり減っていることに気がつきました。
そして、夫に対しても優しくなれました。おそらく、美奈子さんも旦那さんに対してイライラしているのではなくて、ご自身のホルモンバランスが崩れていることで、些細なことにもイライラしやすくなっているのだと思います。
なので、ぜひ赤ちゃんと一緒に外出する機会を増やしてみてください。それだけできっと、旦那さんへのイライラはかなり軽減するはずです!
回答3:家事や育児を「休みたい」と旦那に伝える
私も産後8カ月くらいまでは、いつもとは違った精神状態でした。主人には「触れられたくない」「話しかけられたくない」と思ってしまったり、家事も育児も私が言わなきゃできないし、「主人なんていないほうがいい」と毎日思っていました。
たまに「○○やろうか?」と聞かれただけで、「やろうか?じゃないでしょ。聞かなくてもやってよ!」と強い口調で言ってしまうこともしょっちゅうでした。
ある日、友人にこの「産後クライシス」を相談しました。すると、友人は「その状況、全部旦那に話してみたら?あと、育児も家事も休みたいなら『休みたい』って言わないと、男の人はわかんないよ」と言われました。
私は「えっ?休んでもいいの?」と驚きました。たぶん、「家事も育児も全部、女の私がやらなくてはいけないんだ」という勝手な考えがあったので、かなりのストレスになっていたんだと思います。
その夜、主人に「産後にイライラするのがずっと続いていて、毎日強い口調で言っちゃうんだよね。育児も家事ももう疲れちゃった。お休みしたい」と伝えました。主人は、
いつもよりイライラしているのはわかってたけど、どうしてほしいとか言ってくれなきゃ何もわかんないよ。
家事なんかすぐにやんなくても、俺が帰ってくるまで残しておいてもいいよ。ご飯なんて、なんか買って食べたっていいし。
気分転換したかったら、授乳が終わったらすぐに子供を置いて、出かけたら?オムツ交換はやり方見てたし、任せないといつまでも俺だってできないよ。
と言ってくれました。それからは、「あ~、イライラする!」「疲れた……」と思ったときは、家事をさぼったり、気分転換で出掛けたりしました。私はこれで夫婦の危機を乗り越えられたと思っています。
なので、思い切って、今思っていることや、やってほしいことを伝えてみてください。主人のスキルも上がっていくので、今ではいろいろ任せるようになりました。
回答4:演技をしてでも、たまには旦那に感謝の言葉をかける
うちの旦那も似ているところがあって、家事も育児もほとんど協力してくれません。うちの場合は同居のお姑さんが色々手伝ってくれたのですが、旦那は「母親(お姑さん)がいるから安心」と、余計に何もしなくなった気がします。
抱っこしてもちょっと泣いただけで、「無理!」と言って頑張ってくれませんでした。外食のときも、私は子供をあやしながら、料理の味もわからなくらい手早く掻き込んで食べているのに、旦那は子供には目もくれず、1人のんびりとビールを飲む始末です。
旦那の勝手な振るまいに、当然愛情もなくなりました。子供が生まれたばかりのころはホルモンのバランスも悪いですし、疲労もあります。旦那にまで気持ちは向かないのは仕方ないと思います。
でも、ずっと旦那に愛情が向かないと離婚の原因にもなってしまうので、たまには「お仕事ご苦労様」とか「ありがとう」の言葉を言うようにしました。心の中はイライラでいっぱいでも、たとえ嘘でも、言葉があるのとないのとでは、その後の夫婦関係が変わってくると思ったからです。
子供が2才くらいになって、言葉が通じるようになってきたら、少しずつ自分にも余裕が出て、自然と旦那も受け入れられるようになりました。
ということで、「私は女優!」と言い聞かせて、本当に愛情が戻るまでは演技で感謝の言葉をかけてみてください。
回答5:DVDを借りてきて、2人だけの空間で時間を過ごす
産後クライシスで辛いお気持ち、よくわかります。自分が自分ではないように感じてしまいますよね。
私は2人目を出産後に産後クライシスというか、鬱のようになってしまいました。私は覚えていませんが、「よく1人で窓を眺めながら泣いていたよ」と、母が教えてくれました。当時は辛くても、今振り返ると「あれ?覚えていない……」と言える程度のものです。
だから、大丈夫です。産後はちょっとしたことで悩んだり、不安になったり、イライラしたり、気持ちの浮き沈みが激しくなるものです。
今は、3人目の出産を終えたばかりですが、イライラが収まらずに旦那に強い口調であたるようになりました。自分ばかりが赤ちゃんのお世話に家事に頑張っているような気がして、旦那が飲み会や釣りに少し出かけるだけでも「なんで!?」と怒ってばかりです。
険悪モードが続くので「このままではダメだ」と思って、子どもが寝静まった30分だけでも会話をしたり、一緒にテレビを見る時間を作ろうとゲオでDVDを借りて観ることにしました。(長い作品だと疲れるので、短い作品がおすすめです)
DVDを観ている間の会話はあまりないですが、一緒の空間で時間を過ごすだけでも違いました。DVDは一緒に選びに行くので、出掛ける時間も増えて、気分転換にもなりました。
このやり方で我が家は会話が増えて、危機を乗り切りました。試してみてください。
回答6:産後ケアクラスに参加して、自分の気持ちと向き合う
とてもつらい時期ですね。私も同じような経験をしています。
私は、産後3ヶ月のときに実家から自宅へ戻りました。夫の帰宅が遅くて、やはり出産を機に退職したので、日中の家事育児はほぼ自分ひとりでこなしていました。それに加えて、里帰り中に引っ越したので、毎晩息子を寝かしつけてから次の授乳までの2時間の間に、山のように高く積み上がった段ボールを一人で片付けていました。
そんな鬱憤が溜まって、私も夫に対して「愛情がなくなったかも」と感じるようになりました。この危機を乗り越えられたのは、NPO法人マドレボニータが主催している「産後ケアクラス」に参加したおかげです。産後ケアクラスは、
- バランスボールを使っての有酸素運動で衰えた体力を取り戻す
- 酸素を取り入れたあとのワークでコミュニケーション力も取り戻す
という二本立ての講座でした。このワークを通して、気がついたことがありました。それが、

赤ちゃんとの時間ばかりで、大人との会話がなくて、夫婦間のコミュニケーション下手になっていたんだ。きちんと夫に自分の気持ちを伝えることを忘れていた。本当はこの気持ちをわかってほしいけれど、めんどくさがられそうでそれが怖くて悲しかったんだ。
ということです。それまで働いていたことで対等の関係だったのが、「養ってもらっている」という立場になって、引け目を感じていたことにも気がつきました。産後ケアクラスで同じイライラを持った仲間に出会って、語って、素直に泣くことで、「自分の気持ち」を大事にすることができるようになりました。
その後、徐々に「夫とのコミュニケーションの時間を持とう」という気持ちになってからは、不思議と夫も話を聞いてくれるようになって、関係が改善しました。
なので、お近くに産後ケアクラスがあれば行ってみてほしいです。産後ケアクラスじゃなくても、保育園や保健センターなど、話を聞いてくれる場所はあります。そこで、自分の気持ちをとことん聞いてもらってください。頑張っている自分をいたわってあげることが、夫婦関係の改善に効く、大きな一歩になるはずです。
回答7:夫への愛情を取り戻して、信頼関係もUPさせた方法
私も1人目を出産してから、出産前に比べて主人に愛情はなくなりました。出産前までは、主人のために凝った料理を作ったり、家事を一切させないで私の仕事にしたり、主人に甘えたい気持ちもありました。
でも、出産してからは、家事や育児に協力的でなかったり、亭主関白ぶってるところがイライラするし、なにより不思議と男性としての魅力がなくなって、甘えたいと思うことも減りました。
おそらく、私は家事や育児で精一杯やってるのに、「やって当たり前」と思われて、何の感謝や褒め言葉がないのが、愛情がなくなったきっかけかもしれません。
私が主人へ愛情がなくなったぶん、主人も私に対し当たりがキツくなりました。今まで、喧嘩なんてしたことなかったのに、喧嘩もするようになりました。一時、我が家は負のオーラでいっぱいでした(笑)
でも、「このままでは子供に悪影響だ」と思って、主人に育児に参加してもらうようにしました。方法としては、「育児に参加せざるを得ない状況を作る」ことです。
具体的には、私が家事をやっている間に子供が泣いたら、「ちょっと見てくれる?」「オムツ替えお願いしても良い?」とか、あくまでお願いする言い方で伝えます。あとは、買い物や仕事を理由に数時間や1日だけでも見てもらうようにしました。
すると、主人も最初は仕方なく育児に参加していたのですが、子供と密に接したことで育児の大変さがわかったようで、我が子への愛着に繋がりました。むしろ、今では子煩悩だし、家事も積極的に参加してくれます。
そして、子供と触れ合う姿を見て、主人に対してまた愛情・・・というか、信頼関係が増した感じです。
結局、家事や育児など何も関わりがないと、寂しい気持ちや不安な気持ちになって、愛情が無くなるような気がします。なので、関わりを持たざるを得ない状況を自分から作ってみてください。
回答8:「もう死んでやる」そんな超危機的な夫婦関係を修復した方法
私も同じような状況を体験したので、お気持ちがとてもよくわかります。
1人目を出産後は仕事を辞めて、実家も近くになかったので、家事育児は1人で奮闘していました。夫は、私と産まれて間もない子供を置いて、しょっちゅう麻雀や飲み会に行っていました。職場の同僚と海外旅行に行かれたことは、今でも根に持つほど腹が立った出来事です。
その頃は夫が嫌で仕方なくて、夫自体がストレスとなっていたので、いないほうがマシでした。何度も泣いたし、何度も死んでやろうかとも思いました。それくらい夫婦関係はひどかったです。
そんな私でも、2人目、3人目まで出産することができたのは、ママ友の支えがあったからです。1人目の妊婦時代からのママ友は10年経った今でも大親友です。
そのママ友とは、SNSで私からコンタクトをとって知り合い、何度かランチしたりするうちに意気投合するようになりました。子供が産まれてからは、一緒に買い物や公園に行ったり、沖縄旅行にも行きました(夫抜きで)。
リフレッシュすることを覚えたことで、「嫌いな夫がいても楽しく過ごせる」「自分らしく生きていける」とわかったんです。夫に何も手伝ってもらえなくても全然平気になりました。
その後は、子供を通じていろんな人に出会い、いろんな生き方、いろんな考え方を学びました。そんな中で、
- 自分が満たされていないと他者に優しくなれないこと
- 今の状況を作っているのは自分が望んでやっていること
という2つのことを意識するようになりました。「自分を満たして、自分のやりたいことを明確にしよう」と意識し始めたら、やっと夫にも優しくなれました。すると、夫も自然と私や子供たちに目を向けてくれるようになりました。人間なので、たまにイラっとすることはありますが(笑)、今では夫婦関係は良好です。
以上を踏まえて、美奈子さんが産後クライシスを脱するためには、次の2つのステップをおすすめします。
ステップ1.自分をリフレッシュする
まずは疲れ切ったご自分のケアが必要かと思います。ご実家や一時保育などに数時間でもいいので、お子さんを預けてみてください。
そして、1人でリフレッシュできることをしてください。ゆっくりカフェでお茶をする、美容室やネイルサロンに行く、マッサージや温泉に行く、など何でもいいです。自分に余裕ができると、自然と周りとも穏やかに接することができます。
ステップ2.同じ境遇のママたちと出会う
リフレッシュが完了したら、今度は育児を共にする仲間に出会う場所に出向いてみてください。夫婦関係を見直すには、同じように育児に奮闘するママがどのような生活を送っているのか、どのようにお子さんと接しているのか、をたくさん学ぶことです。そこで同じ価値観のお友達ができたらラッキーです。
こうして、自身の世界が満たされて、いろんな情報を得ることで、初めてご主人に優しい気持ちになれると思います。1日や2日で夫婦関係が劇的に良くなることはありません。少しずつ時間をかけて修復していってください。
回答9:お互いの気持ちを理解し合う「夫婦会議」のやり方
私は産後クライシスにも産後うつにもなりませんでした。それは「旦那の理解」と「旦那の娘への愛情」があったからと思っています。
まず、私は家事を徹底的にサボりました。旦那も「子どもが小さいうちは仕方ない」と理解してくれて、娘が3歳になった今でもそう言ってくれます。旦那は、結婚前「料理だけは嫁がしてほしい」と言っていましたが、子どもが生まれてからは料理や掃除は旦那の担当になりました。
そして、旦那は娘を溺愛しています。週末は必ず遊びに連れて行ってくれます。とにかく娘への愛情が伝わってくるので、それだけでも「旦那が娘のパパでよかった」と思えます。良い夫であるよりも、「良いパパ」「娘を一緒に育てる良いパートナー」であることが私は重要だと思っています。
ですが、旦那も最初から私の大変さを理解してくれたわけではありません。喧嘩もたくさんしました。
特に、娘が100日くらいの頃に、娘の前で激しく言い合いになりました。そのとき、娘が悲鳴のように大泣きしたのです。「大丈夫大丈夫。パパとママは大丈夫だよ」となだめて、やっと泣き止みました。
子どもは、親の表情や気持ちに敏感です。特に、お母さんの緊張や不安は赤ちゃんに伝わって、赤ちゃんの情緒が不安定になります。
それからは、お互いに不満が募ると、言い争いでなくて「夫婦会議」を開くようにしました。夫婦会議では「自分が不満に思っていること」を3つ、お互いに話します。
自分の気持ちは話さなければわかりません。特に、育児を一人でしたことのない旦那は、育児の何が辛いのかがわからないのです。相手が話している間は反論しないで、「うん、うん。そうだったんだ」とすべてを受容する態度で聞くというルールを作りました。
つらさを理解してくれて、旦那から「大変でしょ?」「一人で赤ちゃん見てくれてありがとうね」と言ってもらうだけで、かなり心が楽になりました。お互いに相手にやさしくなって、関係が良くなります。
なので、夫婦で話し合い、お互いの気持ちを理解しあう「夫婦会議」、一度試してみてください。

↓授乳中の人は、この記事も人気です!

トップページに戻る:葉酸サプリクラブ – サプリメントアドバイザーが辛口で評価