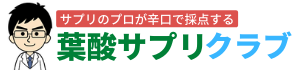安定期を迎えると、安産祈願をするのが日本の習慣です。しかし、しないという選択肢もあります。どちらの選択が良いのか、行くならいつなのか、誰と、どんな服装で、どこの神社に行ったのか、私たちの見解はこうなりました。

3回とも行かなかったけど、子を想う気持ちがあれば問題なし

行く必要なし
マヤ(1979年生まれ/子供3人/看護師)です。私は安産祈願は雑誌で知っただけで、行きませんでした。とにかくつわりが酷かったこともあり、安産祈願まで頭が回らなかったのが本音です。
通っていた産婦人科では戌の日に腹帯を頂くことができ、助産師さんが正しい腹帯の付け方を教えてくれるサービスがありました。
腹帯を付けたことで、お腹を守り安心しきっていましたので、安産祈願までは特に気にすることもなく、悩んだこともありませんでした。安産祈願をしたほうが何かいいことがあるとか、ないとかという問題は全くありませんでした。
「安産祈願に行かないことで災いが起きるのでは?」と思う人もいるのだと思いますが、私は一切気にしませんでした。妊娠中も出産も産後も特に問題はなく過ごすことができました。
結局、一番は気持ちの問題なのです。安産祈願に行かなくても、ママとその家族が赤ちゃんを思う気持ちがあればそれでいいと思っています。安産祈願には3回とも行きませんでしたが、うちの子はみんな健康に生まれ、今でもいい子にスクスク育っていますよ♪
いつも参拝している神社があれば行くべき
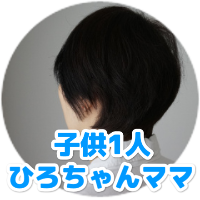
行くべき
ひろちゃんママ(1972年生まれ/子供1人/42歳初産&管理栄養士)です。義理の母が安産のお守りを買ってきてくれましたが、いつも参拝している熱田神社で安産祈祷を受けたかったので、私は行きました。「赤ちゃんが授かりました。ありがとうございます!」という報告もしたかったからです。
ですので、いつも参拝している神社がありましたら、どうぞ妊娠の報告がてら参拝してみてください。気持ち的に安心できますよ!
祈祷自体の価値よりも、イベントとしての価値が高い

行くべき
ヨカっち(1976年生まれ/子供4人/自宅出産)です。私は行ってよかったと思っているので、おすすめしたいです。祈願そのものの価値は置いておき(笑)、自分や家族にとって特別な1日になるからです。私の場合は、祈願に行ったのは初産のときだけですが、強く思い出に残っています。
この行事のおかげで、「初めての妊娠ですべてがワクワクドキドキな気持ち」や、「お腹の赤ちゃんを第一にして過ごしていた幸せな気分」を、10年以上経った今でもはっきりと思い出せます。
行かない場合でも、安産祈願のお守りだけは身に付ける
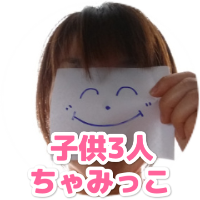
行く必要なし
ちゃみっこ(1976年生まれ/子供3人/調理師)です。私は安産祈願には行きませんでした。そんなに信心深いほうでもなかったし、育児用品を揃えるのに出費がかさんでいたので、なるべく出費を抑えたかったというのが本音です。
周りの先輩ママ達に聞いたところ、「安産祈願に行った。」と言うママさんと「安産祈願には行かなかった。」と言うママさんが、半々くらいでした。特に、旦那のお姉さんが安産祈願に行かなかったのが行かない決め手となりました。
うちの場合は、旦那の両親と同居しているので、何でも義父母に相談をしていました。
「戌の日にはどのようなことをしたらいいですか?」と、相談したところ、「私たちのころは、戌の日には産院で安産の腹巻きを巻いて、安産祈願をしてくれたのよ。産院でそのようなことをしてもらえるか聞いてみたら?」と言われました。義姉も特に問題なく無事に安産だったので、うちも大丈夫だろうと思いました。
また、知識の乏しかった私は、義母に言われるままに産婦人科病院で聞いてみたところ、「うちの病院ではそのようなことはしていません。妊婦帯もお腹を締め付けることになるため、おすすめしません。」とのことでした。
過去記事:人気の腹帯(妊婦帯)はどれ?実際に付けてわかった必要性とデメリットも教えます!
犬印の腹帯を自分で巻こうと思っていたのですが、その話を聞き、腹帯を巻くのもやめてしまいました。周りの意見に流されるように、安産祈願には行かなかったのですが、やはり少し気にはなりました。、「安産祈願をしたほうがいいのかな?何か良くないことが起こったら嫌だな・・・」とは、少し思いました。
そこで旦那に相談すると、心配して安産祈願のお守りを買ってきてくれたので、いつも身に付けていました。安産祈願をしなくても、お守りのおかげか無事安産でした。
なので、安産祈願に行く余裕がない人には、ぜひお守りを身に付けることをおすすめします!きっと良いが出産できますよ。
誰に相談してもスッキリしない・・・そんなときは神様にお願い

行くべき
なな(1989年生まれ/子供1人/元婦人科看護師)です。「妊娠」や「出産」は、色々と不安を感じることがあります。誰に相談してもすっきりしないときには、安産祈願のときにもらったお札(ふだ)に手を合わせて「どうか無事に生まれますように」とお願いするだけでも楽になった気がしました。
ご祈祷も受けているので、それも含め「神様が守ってくれる!」と思えて、心強かったです。私は安産祈願に行ってよかったと思っているので、行くことをオススメします!
安産祈願をきっかけに、夫に父性が芽生えた

行くべき
あ~ちゃんママ(1981年生まれ/子供6人/安産の達人)です。ずばり、行ったほうがいいと思います!5人目までの安産祈願は、なんとなく形式的に行っていたのですが、6人目のときの経験はとてもいい思い出になっているからです。
夫に一緒に行って同じ経験をしてもらって、改めて「無事生まれますように・・・そしてお互い子育て頑張ろう!」と、気持ちを一つにするとってもいい経験ができました。
妊娠中は、男性はなかなか親となる自覚が芽生えにくいと思いますが、安産祈願をきっかけに「お腹の中でもう子育ては始まってるんだ」と夫に思ってもらえます。さらに自分も嬉しくなるような経験ができて素敵です!
実際、そんな経験ができたあとの我が家では、夫がとても積極的に赤ちゃんとの関わりを持ってくれました。お腹に話しかけることも多くなりましたし、私を気遣ってくれることも多くなりました。
素敵なマタニティライフを送れるいいきっかけになったので、ぜひ旦那さんと行ってみてください。
安産祈願に行かなくても、5人全員元気に誕生

行く必要なし
あきママ(1983年生まれ/子供5人/双子出産)です。私は安産祈願には5人とも行きませんでした。初めての妊娠のときは行くつもりでした。5か月目に入ったころからどこの神社がいいのか、主人や家族と相談していました。
「これから子供と暮らしていく近所の神社がいいよね」「いや、安産祈願で有名なところがいいんじゃない?」と、みんなで意見を言い合って、考えているうちに妊娠8か月に入ってしまいました(笑)
もうお腹も大きくなって、ちょうど暑い時期と重なったこともあり、「安産祈願はしなくてもいいか」という結論になりました。2人目からは、育児の忙しさから、安産祈願のことなどすっかり忘れてしまって行けませんでした。
一度も安産祈願に行きませんでしたが、5人とも無事元気に産まれてきてくれました。大きなケガ、病気もなく成長してくれています。妊娠中は体調も安定しないことが多いのに、新しい家族を迎える準備でやらないといけないことはたくさんあります。
なので、「余裕のない時期に無理して行かなくも大丈夫ですよ」とお伝えしたいです。日々の生活の中で赤ちゃんが無事うまれてきてくれるよう願っていれば、お腹の赤ちゃんにもちゃんと届きますから、安心してください。
堅苦しいことが嫌いな主人も納得の1日

行くべき
はらだひな(1988年生まれ/子供2人/身内に助産師)です。私は安産祈願は行ったほうがいいと思います。実際、私は行ってよかったと思ってますし、無事2人とも安産だったからです。神聖な場所でのご祈祷は、心も体もすっきりしました。
神社マニアだけど堅苦しいことは嫌いな主人でさえ「行ってよかった!」と言ってました(笑)これから迎える新たな命が無事生まれてくることを祈るのは、親になった自覚をさらに与えてくれる気がします。
安産祈願をした長男が、瀕死の状態で産まれて思ったこと

行くべき
こじかママ(1985年生まれ/子供3人/元看護師)です。私が安産祈願に行ったのは長男の時だけです。長女次女の時は、子育てや仕事で忙しくて行けませんでした。でも、長女次女は安産でした。
その一方で、安産祈願をした長男は難産で産まれてきました。産まれてきたのに息をしていなくて、10分ほど蘇生をしていました。先生も必死に蘇生をしてくれたので、ちゃんと息をして泣き出してくれました。
(参考:私の出産体験記:年に一度あるかの難産で、仮死状態で生まれた赤ちゃんが蘇生するまでの話(こじかママ))
心のどこかで、「この子は絶対に死なない!」と思いました。私の母も主人も立ち会っていたのですが、二人とも「絶対に死なない!」と思ったそうです。
あとで私が、「安産祈願に行ったのに難産だったよ・・・」と言うと、母は「安産祈願に行ったから、長男は息を吹き返してくれたんじゃない?安産祈願に行ったから、みんな絶対に死なないと思ったんじゃない?」と言いました。
確かにその通りだと不思議な気持ちになりました。私は安産祈願をしたら難産で、しなかったら安産でした。ですが、安産祈願に行ったことで、「長男を守ってくれた」と感じています。なので、時間の余裕があるなら、行っておいたほうが良いです。
出産のときの余裕のない場面でも、心の安心感につながることは確かですよ。